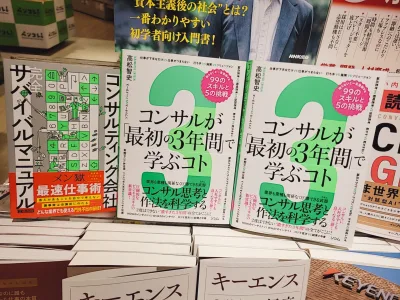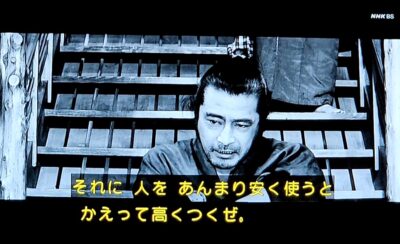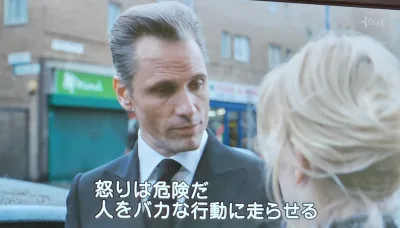2024年6月9日 20:29
生物シリーズ第二弾。プラネットアースより。

モンゴルの平原に生息するサイガという牛の一種。
こんなに面白く、可愛い顔をしているけど、、
メスとエサ場を巡って、
凄まじい勢いでオス同士が戦う。草食獣とは思えない。
オスは、戦いに負けると、
すべてを奪われる。子孫を残せない。
サイガに限らず、多数の生物がそうなっている。
強いオスだけが、子孫を残せる。
人間は、その点、恵まれている。
武闘力以外の要素でも、子孫を残せるからだ。
オスはつらいよ。
男はつらいよ。。
https://cleaning-keiei.com/nakanishi/2019/12/21/
以前、サラブレッドの章でも書きました通りです。
走らないオス、馬肉になるのみ。
オスどもよ、
ちゃんと、稼ごう。仕事しよう!
2024年4月13日 20:17
どうでも良い事の中に、ヒントがある。
時々、このブログにあらわれる、何、食べたシリーズ。
こちらは、通りがかりに、ふと入ってみたお店。
何と・・・「天ぷら」と「刺身」を同時に、丼のうえに乗せるという「暴挙」?
よくばり丼・1200円

定食として、別皿でセットされるのは、
上級ランチとして、広く認知されるところでありますが。
歌手で言えば、矢沢永吉と松山千春を、
デュエットさせた、というようなものである。
そして、
注目すべきは、この「よくばり」の下にある。
野菜天丼480円。
腹ペコで、お金に余裕のない学生君のためのメニューが、ちゃんと存在しているのです。
かっこつけてない、チャラくない、
お客様に密着して、
地道に積み上げるこのお店の姿勢が見て取れます。

裏面は、こうなっています。
2024年3月17日 21:07
10年以上前から、大学生の就職したい業界に
「コンサルティング業界」が、ベスト10入りしている。
ある大学生向け就活サイトより、最新の人気業界。
1位:IT・ソフトウェア・情報処理
2位:広告・出版・マスコミ
3位:食品メーカー
4位:商社(総合)
5位:人材
6位:コンサル
7位:金融
8位:サービス
9位:商社(専門)
10位:官公庁・公社・団体
今、本屋さんに行けば「コンサルタントになるための本」が、各種ずらりと、売られている。
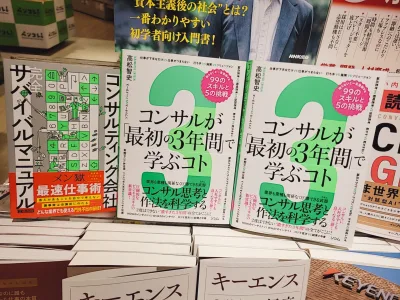
ササーッと、読んでみました。
良いことが書いてあって、今の自分も改めて参考になる・・という内容でした。
が、どの本にも、最も大事なことが抜けている!
これじゃ、普通のコンサルタント止まりだね。
1994年、就職活動していた当時、
コンサルティング業界なんて、自分で探さなきゃ、どこも求人募集していない・・そうゆう業界だった。
学生なんか使い物にならない、中途採用、専門経験者でないとダメ。という会社が多数でした。
新卒から約30年、この道でやってきたおじさんが、
コンサルタントにとって、一番大切ことを、教えて進ぜようー。
おじさんの本を買って、読んでね、
自分なりの答えと仮説を持ってきたら=本気なら教えます。
2024年3月2日 21:17
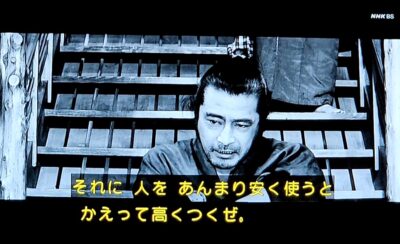
今回も、映画より、
私が気になった名言シリーズ・・・・
黒澤明の映画「用心棒」より。三船敏郎扮する用心棒の言葉。
「人をあんまり安く使うと、かえって、高くつくもんだぜ」
経営者の役員報酬の比率って、
どのくらいが最適なものでしょうかね?
幹部や正社員さんの年収と比較して。
仕事内容と比較して。
もちろん、年商規模や利益率にもよるのでしょうが。

私は「用心棒」役として、
その割合、比較数字が、適正な経営者さんと、
きちんとお付き合いがしたい、
また、そうでなければ、これからの時代、不倒の会社は作れない。
かえって、高くつくぜ!
覚えておきましょう。
2024年2月24日 21:06
京都大学と吉田寮は「プロレス」している。
「トムとジェリー」のようなものである。
↑↑夢のない現実主義者の私が大好き、数少ないアニメである。
(仲良くケンカしな♪)ということである。
つまりは、
文春と松本も「プロレスのようにやってほしい」ということが、言いたい。
結局、共存共栄なのである。
どちらかが、倒れるまでやっちゃダメなわけで。
「生きる道」を残しつつ、
双方で「作品」「歴史」を作れば良い。
コンサルティングにおける私の得意分野である「競合店との戦い」
その特長のひとつは、
こうゆう「プロレス要素イメージ」も、頭にいれながら、行っていることにある。
100%以上、120%のパワーを注いで、
「クライアントが勝つこと、生き残ること、売上・利益が上がること」
そのためには「競合店からお客様を奪い取ること」を至上命題として、
生々しく、シリアスで、現実味あふれる支援している。
しかし、さらに、その上に「30%くらいの足し算」で、
競合店との「闘争」を、
プロレスや、トムとジェリーのように、コミカルにも考えながら、施策を考える。
徹底的に自らの存在をかけてトコトンやる!! でも、そのなかに、
自社と競合他社が入り乱れて「市場」という「作品」を、共に作り上げていることを、
俯瞰して考える。
プロレスや、スポーツなどで、全力の戦いを観たお客様が、盛り上がって喜んでくれているのと同じように、
消費者が、同業者同士の真剣な戦いを見て、盛り上がってくれることを、視野に入れる。
(おおー、やってるなー。どっちを応援しようか・・・)
そのなかで、私のクライアントを応援してもらえるように。
それを足し算して、戦いを進める。
(お、ライバルはそうきたかー。そうすると、次は、こうなるな。。)
それを見た観客(消費者)は、こうゆうイメージを持って動くから。。
なんてことを、やっている。
商売における、勝ち負けは、お客様の支持の獲得。
=お金を払っても良い。と思われるかどうか、なのである。
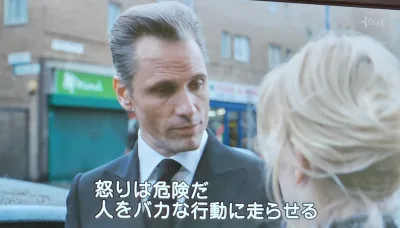
・・・・
小学生、中学生のとき、
発狂したように必死で本気でケンカするヤツを、周りのみんなは支持しない。
勝っても、負けても、引き分けでも、
可愛げのあるヤツ、優しさのあるヤツ、筋の通っているヤツ、戦い方に優れているヤツ。卑怯ではなかったヤツが、
長い学校生活のなかで、みんなに好かれていた。
そうでないヤツは、長期的に見れば、支持が集まらない。
法人だって、そうゆう感じである。