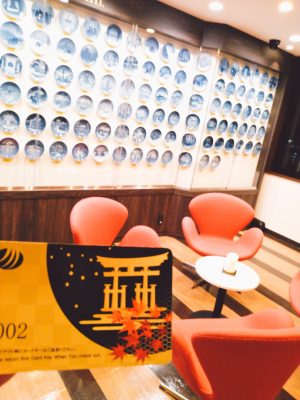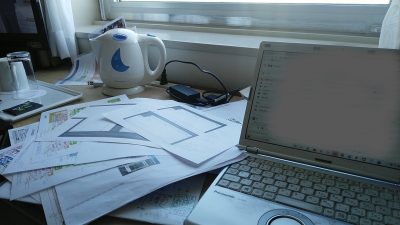2021年3月21日 22:55
この春、若者は、高校を卒業した。
「高校生活を、本当に満喫できた!」
「一切の後悔がない。剣道で近畿大会の一歩手前で負けたことを除いては」との感想で。
そうか、そうかー
青春を謳歌しているなー!
これ以上の喜びはない!
3年前…高校入学直前の彼に
「手紙」を書いて、渡しておいた。
その内容のことも、覚えてくれていて、
「参考にしたで!」と、感想に付け足してくれた。
その手紙は、A4サイズで、5枚程度のもの。
書き出しは、以下の文章から始まる。
↓↓
鳥が空から地上を見渡すことを「鳥瞰・ちょうかん」すると言う。
「俯瞰・ふかん」するとも言う。
「上の方からできるだけ客観的に見ること」という意味。
目の前のことに必死だと、全体の中で、自分がどこにいるかわからず不安になる。
進むべき道もわからない。
しかし「俯瞰・鳥瞰」して見れば、これから、どう進むべきか?が、
効率的に理解できる。
巨大迷路ゲームの中で、右往左往する人と、
それを上から見ている人の違い、を思い浮かべればいい。
ほんの少しだけ長く生きている人間として「高校生活」が、どんなものか、
これからの人生の中で、どうゆう位置づけなのか?を伝えておきたい。
人生を「俯瞰・鳥瞰」したときの自分なりの考えなので、参考にして欲しい。
↑↑
この冒頭文章、以降の主な目次は、以下の通り。
・「受験」の意味。合否よりも、格段に大切なこと。
・人生のなかの「高校生活」唯一無二の特徴とは、何か?味わい尽くせ。
・本屋に行く男子は、かっこいいぞ!
・両親(ジジババ)の教え=俺もその通りだと思う中西家の教えを、そのまま伝える。
・友達について。俺の反省を踏まえて、聞いて欲しい。
・恋愛について。フラれたり、落ち込んだときには、これを思い出してくれ。
・部活動について。目標を共有し、体をぶつけあう=一生の友ができる。
・心配なことが、ひとつだけある。これだけは頼むぞ!
・・・・・
充実した高校生活を、後悔なく楽しんだ。と、本人が自認し、
この春、難関大学にも挑戦し、第一志望に合格し、4月から大学生となる。
その本人が、少しは役立った。と言っているなら、
手紙と成長は「成功例」と言って良いのではないか。
既に、高校を卒業したので「守秘義務」も果たしただろう。
もし、この手紙の全文が欲しい方がいれば、
お口が堅い方、門外不出の約束が守れる方、末永く仲良くさせていただける方に、
お送りいたします。
ただ、、相当、偏った内容で、オモテに出せなさそうなことも多数。。
ノンクレームにて、お願いいたします。
気分を悪くされそうな方は、ご遠慮ください・笑
2021年3月20日 20:37
白のボディに、赤の内装。。
オシャレ社長の隣に同乗。
助手席前にある、これ。。何ですか??

ポチッと押すと、
中から、カップホルダーが出てきました。

で、元通りに収納できる。
おおーー。電動でもなく、
シンプルな作りで、とてもよくできている。
すごいなあ~。

各国の車に乗っている、この社長が教えてくれた。
ドイツ人は、こうゆうことを考える。
アメリカ人は、カップホルダーを、どーーんと作る。
イタリア人は、カップホルダーを作らない。
なるほど・・・
的をえている感じがする。
2021年3月6日 21:09
昔、もう20年以上前、
とある駅前の、古臭いビジネスホテルに泊まったことがある。
百万人都市の主要駅でありながら、
昔ながらの面影をそのままに残している駅前で、
「なんか、面白いことが、あるんじゃないか?」と、
ブラブラ歩くのが好きだった。
タイムスリップしたか、
アジアの街に瞬間移動したような感覚があった。
穴の開いた、ビニールシートのアーケード。
果物屋さんや、おもちゃ屋さん、金券ショップに、サラ金屋さん。。
雑居ビルの上には、ネオンと看板が立ちならんでいた。
最近、再開発が進み、
この「闇市風」駅前の一画は、
巨大商業ビルや、タワーマンションとなってしまった。
(あの、さびれたビジネスホテルは、どうなっただろう??)と、
気になって、調べると、まだ、あった!
巨大ビルの数フロアを、自社のものとして営業していた。
おそらく、地権者であったのだろう。
館内も、当時とは全く異なる、
ハイセンスな作りになっている。
(改装にあたり、優秀なコンサルタントが入った“匂い”がする)
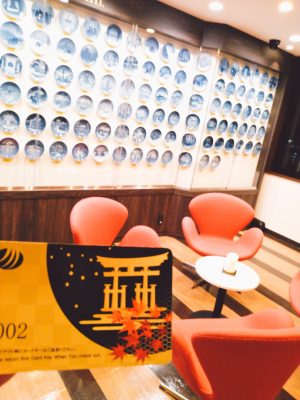
そして、ロビーには、
「見ろ!」とばかりに、高級陶磁器ブランドのコレクション。
おお~、
あんなボロボロの貧乏ホテルに見えて、
しっかり、貯め込んでいたんだな・・・(笑)
きっと、経営者の自宅のコレクションを見たコンサルタントが、
「これ、使えませんかね??」
「家に飾っておいても、お金は生みませんよ」
「本当に大事なものだけ、とっておいて、他は会社に貸し出してください」と、
言ったのだろう・笑
人は、見た目や、持ち物だけで判断できない。
豪邸に住み、高級車に乗り、
ピカピカの店舗を作っていても、
その実、中身は借金まみれで、火の車。。なんてことのほうが、多いかもしれない。
その逆のことも、たくさんあるわけです。
2021年2月27日 10:05
ホモサピエンスは、
氷河期の絶滅の危機。。
アフリカの最先端に移動。
貝を食べて、生き残った。と言われている。
見慣れぬものを食べてみる勇気。
好奇心の強いものが、生き残る。
2021年2月21日 22:14
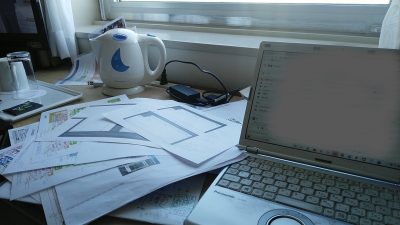
2月中旬、ついに、
1日で、返信すべきメール受信件数が100件を超えた!
1本10分かかるとすれば、
1000分=1日16時間。
8時間くらいはクライアント先に行ってるから、
ちょうど、うま~い具合に、完全に1日=24時間で終わる計算である・笑
ただ、内容は、単に質問に答えるものでなく、
販促物(=武器)のラフ案、提出。販促物の校正。
新店舗(=戦艦・城)のラフ案、校正。
数字データ分析、対策。。に関することが含まれているので、実際は、もっとかかる。
コロナ感染者数・入院患者数のように表現すれば、
「ひっ迫」「緊急事態宣言」である。(笑)。
ところで、
「ひっ迫」→「崩壊する」と言われている、
コロナ重症患者のベッド数は、70%台から、上回ることはない。
普通に考えれば、1月の時点で100%を超えているはずである。
どこかで、調整したり、やり方を変えたり、頑張ったりしている。
個々人レベルで、ひと息も入れている。
実際は、100%を超えているかもしれない。
けど、
100%を超えないように、自助調整しているのである。
社会人になってからの1年~3年で、
そうゆう「24時間では、とても終わらない仕事の現場」を、
たくさん経験してきたから、
そのあたりの数字には出てこない要因や、切り抜ける方法、
心の持ち方が、わかる。
ひっ迫状況のなか、
嬉しいのは、成果が上がったこと。上がりそうな兆しが見えること。
それに、共に協力してくれるメンバーの存在である。
医療現場の皆さんも、
回復しようと頑張っている患者さんや家族の姿。
その結果、無事回復した姿。
大変な中、共に協力し合う、周囲のスタッフの存在。
こうゆうものが、ちょっとした、いや、大きな助けとなって、
乗り切っているんじゃないかなー。