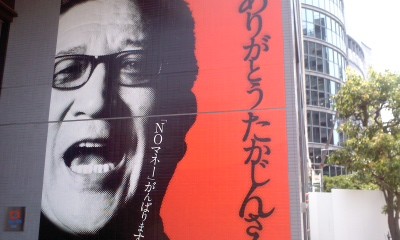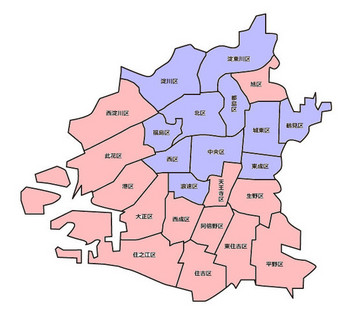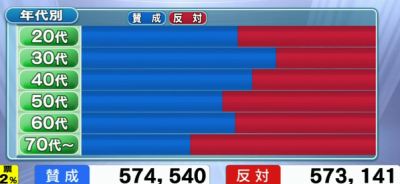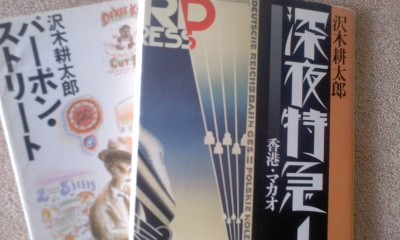2015年5月24日 21:01
九州のクライアントさんへ。
素敵な海辺のお蕎麦屋さんに、連れていっていただき、昼ご飯。
ロケーションも、器も、味も、素晴らしい!

ところで・・・
会社を発展させる経営者の見分け方があります。
普段、自分が、滅多に行かないような食事場所に、
コンサルタント(=取引業者)を連れていってくれる経営者の会社は、
儲かっていない。
特に、利益が出ていない。
儲かっている会社の社長は、
普段から、自分が食事している場所で、
コンサルタントと、昼ご飯を食べる。
特別な場所で、ご飯を食べるのは、
あったとしても、
年に1度くらい、良い決算であった年だけ。
社長が、普段から一流ホテルで食事をしているなら、一流ホテルの食事で、良いのです。
普段、料亭で食べているなら、料亭で、OK。
ラーメンを食べているなら、ラーメンでOK!
スーパーの弁当なら、スーパーの弁当を、一緒に食べれば、それで良い。
「せっかく来てくれたのだから・・・」と、
背伸びをして、連れていってくれようとする会社は、
確実に、儲かっていません。
つまり、儲かっていない会社の社長は「良い人」なのです。
一般人としては、合格かもしれない、
しかし、経営者としては、失格。
気持ちは、とても嬉しいのですが、
その経費を節減して、売上につながることに、お金を使って欲しい。
その本質=優先順位のつけ方を、理解して欲しい。
失礼を承知で、そんなことを、直言させていただきます。
スタッフが「夏、暑いからクーラーを買って欲しい」と言ったとき、
すぐに、買う決定をするのは、儲からない会社。
「扇風機でガマンできないか?」
「冷風器なら?」
「出勤時間を早めては?」
どうしても、お金を使わなければならないなら、「決算で利益が出そうなら」。。
トコトンお金を使わないで済む方法を、
経営者・幹部はじめ、
スタッフ全員考えることができるのが、儲かっている会社。
美味しい食事が遠のく、
自分の首を絞めてしまう記事を書いてしまいました。(笑)
2015年5月19日 22:05
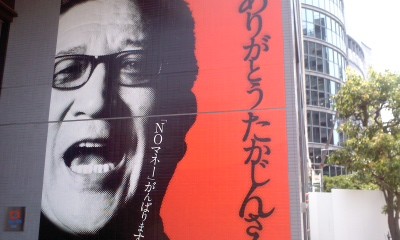
「中西さん、橋下・都構想の敗因は、何ですか?」と、尋ねられると、
冗談まじりに、
「やしきたかじんさんの死ですよ!」と答えます。
たかじんさんの死から
一気にパワーダウンした気がしてなりません。
大阪以外にお住まいの方には、想像がつかないくらい、
大阪では「地元タレント」の発言力が、強いのです。
やしきたかじんさんは、
間違いないなく、大阪のオピニオン・リーダーであり、ソウル・ヒューマンでした。
お気に入りの曲は、これ。
「あんた」
たかじんさん自身が、泣けてしまって歌えないので、
人前で歌うことを、何十年か、封印していた幻の曲。
「引退前、最後に歌う」と言っていましたが、
かなわず、他界されてしまいました。
ところで・・・
橋下さんの「スッキリ笑顔」の敗北会見・・・。
あの「笑顔」に、ちょっとした違和感を覚えませんでしたか?
何だろう???
「もう、キミら(大阪府民)には、付き合い切れへんわー。」
「俺以上に、本気になってやれるヤツがいれば、探してみたら?」
裏側に、
そんな気持ちを秘めた笑顔ではなかったのか?
なんて、感じます。
2015年5月17日 23:53
反対が、僅差で勝利しました。
各地のご支援先からは、
「なんで賛成が勝たなかったの?」とか、
「大丈夫か?大阪市民は・・・」との声をいただきます。
興味深いのは、賛成・反対の内訳データ。
地域(区)別に見れば、
北エリアが「賛成」多数で、
湾岸~南エリアが「反対」多数。
大阪市内の地図が、くっきり2つに分かれています。
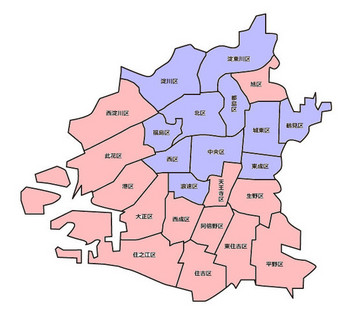
世代別に見れば、
70代以上が「反対」多数で、
それ以外のすべての世代は「賛成」多数。
ただ、この数字は、出口調査の結果なので、正確なものではありません。
ちょっと、怪しい数字です・・・。
「傾向」を知る程度にしておいたほうが良いでしょう。
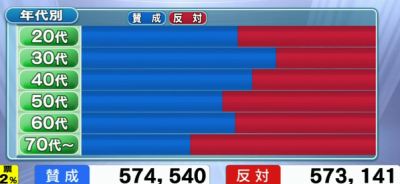

私自身も、大阪市民ですが、
「目の前のこと」を重視すれば、反対です。
「未来の可能性」に懸けてみたいなら、賛成です。
実際、大阪では、橋下さんがリーダーとなってから、
「無駄」と判断された、行政サービスが、次々と
全体の黒字化のために、削られています。
今、享受しているメリットを受け続けたい。
現に、橋下体制となってから、メリットを削られた、
きっと、これからも削られるだろう。
生きているうちは、これまで通り、平穏無事に過ごしたい。。。
こうゆう住民が、若干、多かったということです。
今か、未来か。
個人か、全体か。。。
これからの大阪が、
ちょうど、1年前のブログにも書いた
「Aでも、Bでもない、より発展したCを作り出す」
そうゆう方向に進んでいってくれればなー。と、思います。
2015年5月11日 23:43
「プラシーボ効果」
薬の成分が入っていないも偽モノの薬でも、
お医者さんから出されて、
「効果がある」と信じ込んで飲めば、実際に効果が出る。
という治療効果であり、心理効果でもあります。
プラシーボとは「喜ばせる」の意味。
クリーニング屋さんの店員さんに、
「キレイに仕上がっていますね!」と言われると、
実際以上に、キレイになっているように感じる。
チラシやポスターに「お客様の声」を、
掲載するのも、プラシーボ効果を狙ったもの。
優秀なコンサルタントに、
「大丈夫です、売上は上がりますよ!」と言われれば、
実際以上に、効果が出る。。。(笑)
そう、信じてもらえる実績と雰囲気を持つ、
コンサルタントになりたいものです。
最近、「逆・プラシーボ効果」を体験しました!!
ゴールデンウィークから、寝ているときも、咳が止まらなくなったので、
たまらずお医者さんへ・・・・。
すると、そのお医者さん
・白衣を着ていない、普段着のオッサンが、面倒臭そうに診察する。
・診察中に、平気で携帯電話に出る。メールチェックをする。。
「なんだ?この医者・・・」と思うと、
薬も効かないような気がしてくるのか・・・!?
やっぱり、治りが悪いので、
大きな病院へ行くことにしました。
しかし、大きな病院は、豪華施設で、人気がありすぎなのです。
ピアノがあり、庭があり、カフェがあり・・・。

診察開始30分前の、朝8時過ぎに受付を済ませたのに、
診察室に通されたのは、13時30分!!
待ち時間、なんと5時間・・・。
「待つ」ことが、何よりも嫌な性分なのに。。。
でも、今度は、
先生を信じて、薬を飲もう!
そうすれば、薬の効き方も、違うはず!
「これで、きっと良くなる!」という心理効果。
人生の全てにおいて、プラシーボ効果を味方につけましょう。
=「セルフ・プラシーボ」ですね。
そして、
周囲に「逆・プラシーボ効果」を、
与えてしまわない人になろう。
2015年5月5日 6:34
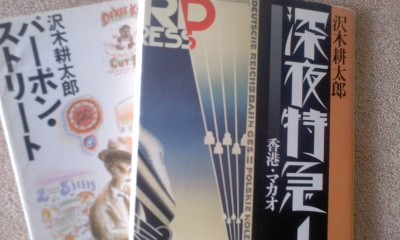
「ゴールデンウィークは、本を読もう!」と、決心するも、
新しい本を買って、読むほどの気力と時間は、残されておらず・・・
昔、読んだ本のなかで、
捨てずに置いてある「マイ・セレクション」を、
引きずり出して、気楽に読むことに。
人生の放浪癖・・・というか、
「俺は、リュックひとつで、どこでも楽しく、生きてゆける・・・」と、
心のどこかで思っている(悪しき?)自分を作っている一要因が、コレ。
・・・沢木耕太郎さんの本。
毛が生え始めてから、
身長が止まるくらいまでのうち=10代前半~20代前半、
いわゆる思春期に出会った人や、本は、
人格形成に、大きな影響を与えるみたいです。