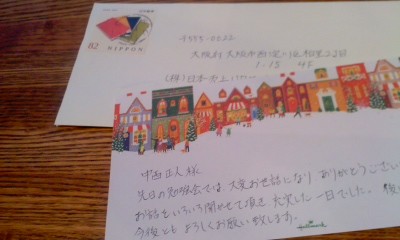2015年4月3日 23:05

写真は、何年か前に行った、甲子園。
甲子園の、この位置に立つと、ドキドキ・ワクワク感が、最高潮になります!
「解説者で楽しむ」のは、高校野球も同じ。
特に、夏の甲子園の民放では、名門校の監督が、ゲスト解説者に呼ばれます。
それぞれの個性が出ていて、とても楽しいのです。
人情派、熱血漢がいれば、理論派もいる。
投手重視もいれば、打撃重視もいる。機動力重視も。。。
解説が本職ではないので、
結構、ズケズケ言っちゃう監督さんもいて、楽しさ倍増なのです!
特に、年配の監督さんは。
経営の参考になるかもしれない、面白かった解説をひとつ、ご紹介します。
解説者は、広島・如水館高校の監督・迫田穆成(さこた よしあき)さん。
元・広島商業の監督として有名です。手堅いバント戦術の生みの親。
怪物・江川の作新学院に、わずか2安打で勝利したことは、野球ファンの間では伝説です。
アナウンサーが質問する。
「迫田さんは、大所帯の野球部を、どうやって把握しておられるのですか?」
「全員まで、目が行き届かないことは、ないのですか?」
迫田さん、答える。
「それはねえ・・・、スパイを作っておくんですよー、グヒヒヒヒ・・・」
ア)「スパイ?、どうゆうことですか?」
迫)「監督がね、直接聞いたところで、そんなもん、選手はホンネを言いませんよ。」
「マネージャーあたりを、スパイにしとくんです」
「そこから、色んな情報を、こちらの耳に入れてゆくんです」
「これで、だいたいのことは、把握できます」
ア)「もし、不満を持っている選手がいたら、どうするんですか」
迫)「それは、チャンスですね~」
「呼び出して“オマエ、最近思うとることがあるんやないか?”と聞いてやるんですよ」
「オマエの意見を聞かせて欲しい、こうゆうてあげたら、もう次の日からチームのために、一生懸命やりはじめます」
いやー、さすがです!
・・・・
これは、スタッフ20名以上の規模になれば、必須のマネジメント法ではないでしょうか。
そう言えば、、、
前職の船井総研時代の役員で
「なんで、普段、会社にいないのに、そんな小さなことまで、知ってるの???」という方がいました。
500名規模の組織のあらゆる部署で「何が起こっているのか」を、
ほぼ完ぺきに、把握していました。
あれも・・・・間違いなく、営業事務スタッフを「スパイ」にしていましたね。(笑)
2015年3月20日 21:43
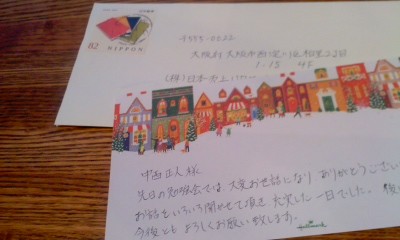
会社に届いていました!
かわいい封筒に、手書きの文章。
勉強会にご参加いただいていた方からの「お礼状」です。
とても嬉しいです!
メールが中心となってきた世の中だからこそ、
受け取った側は、ぐっと心動かされます。
ワタシも、
うちの会社メンバーも、
何とか、やってゆきたい・・・。
これを、
ずっと、続けてゆけば、人生が変わることは、確実。
うーん、
何とか、しないと。
2015年3月7日 22:00
新聞記事より・・・
コンビニ業界3位のファミリーマートと、
4位のサークルKサンクスの、合併ニュースが出ていました。

共同仕入れ、システム共有による
スケールメリットで利益を出してゆく・・・との主旨。
「ひとつの業種で、地域の中に生き残れるのは上位3社まで。」
いよいよ、そんな時代が本格化する予感が、現実味を帯びてきました。
クリーニング業界の主流も、このようなカタチになってゆくことでしょう。
買収・合併が相次ぎ、店名はそのままでも、
「実は、洗っている工場は同じ」で、原価を削減する。という構造です。
ところで、
この新聞記事から、数字を拾って、アレンジしてみました。
「売上÷店舗数」で、「1店舗当たり年商」を出し、
さらに、その年商を、営業日数365日で割って「平均日販」を算出したものです。
1店舗・平均年商 日販 ※別のデータより
セブンイレブン・・・・・・・・2億1885万円 59万円 (66万円)
ローソン・・・・・・・・・・・・・・1億4484万円 39万円 (54万円)
ファミリーマート・・・・・・・1億5277万円 41万円 (52万円)
サークルK・サンクス・・・1億3200万円 36万円 (43万円)
()カッコ内は、私が別で持っているデータからも、日販を計算してみたもの。
誰かによって公表されている数字は、絶対に、鵜呑みにしない!
・・・という、この性格の悪さ!!
さらには、
セブンのこの売上には「どこまでの売上をいれてるの??
セブン銀行の手数料とか入れてるんじゃないのー」という意地悪な視点・・・(笑)
私が計算したデータが少し古いせいなのか、数字には開きがあります。
が、セブンイレブンの圧勝には、変わりがありません。
しかも、増税後、セブンイレブンだけが、売上を伸ばしていて、
他のチェーンは、売上を落としているそうです。
なぜ??
その理由を、考えてみましょう!!
2015年2月27日 22:27
最近、菓子店の繁盛店で、増えています。
通常のショーケースよりも、少し「高めの位置に棚」のあるタイプのショーケース。

商品そのものに、とてもインパクトが出ます。
ぐぐーっ、と前に出てくるような存在感を演出してくれます。
小売業の陳列の基本原則に、
「ゴールデンゾーン」というものがあります。
お客様の手に取りやすい位置
(女性の場合、約60cm~150cm・・・首から腰くらいの位置)が、ゴールデンゾーン。
この高さに、商品を陳列すると、良く売れるようになるのです。
ここに「売れ筋・商品」「売り筋・商品」「儲かる・商品」を、
陳列し、売上を最大化してゆきます。
このタイプのショーケースは、
「ゴールデンゾーン」の陳列原則に、基づいたアイテムです。
できるだけ、お客様の目線に近いところで、商品を見せることができるようになっています。
流通業界やマーケティングの「常識」と言われていることが、
各業界では、まだ実践されていないことがあるみたいです。
クリーニング業界でも、
再チェックが必要ですね・・・。
2015年2月17日 8:42
「経営に関して、とっても本気」で、
尊敬できる社長に、教えてもらったことを、ご紹介します。
「罰金制度」を作ることにしたそうです。
目的は、制度によって組織をコントロールすることや、
不正を起こさせないようにするためではなく、
「やってしまった」スタッフへの信頼感を、失わないようにすること。
つまり、「罰金」を払った時点で、
スタッフへの気持ちを、いったん「クリア」にできる。
「アイツは、こうゆうヤツで・・・」と、人格にレッテルを貼り、疑ってかかってしまわないように。
「罰金も、払ったし、次からしないように・・・」と、前を向いて進んでゆけるようになるために。
同様のことは、
「始末書」にも、言えます。
組織によっては、スタッフに「始末書」を書かせることが、
目的になっているような組織もあります。
そこまでではなくとも、
スタッフに「始末書」を書かせることに、達成感を感じているリーダーもいる。
「はい!始末書、書きなさーい!!」
スタッフに、始末書を書かせざるを得なくなったときに、
心が痛む・・・「あ~、コイツに始末書、書かせることになってしまった・・・」と。
自分の責任のほうを、大きく感じるリーダーでなければならない。
「スタッフへの信頼感」を、失わない、
「顧客への良質なサービス」を、提供し続けることのできる組織や制度を
どうやって作ってゆくのか・・・。
会社経営の永遠の課題に、ヒントをもらいました。