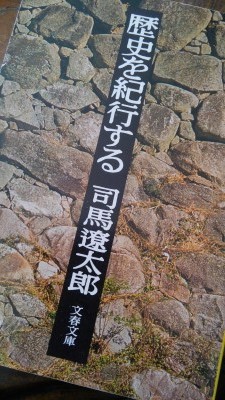2016年7月31日 21:38

知らぬ間に、馴染みになっていた
天ぷら屋のオヤジさんの工夫。。
極小店舗ならではの取り組みですね。
「店が狭い・・・」と嘆くだけでは、何も変わらない。
そりゃ、広い店・新しい店・豪華な店が、良いに決まっている。
「お金がない」「暑い、寒い」「景気が悪い」・・・
それらは全て「与件設定=与えられた条件」で、
まず、その中を限られた条件のなかで突破しないと、
与件そのものを変えることは、永遠に不可能だ。
知恵は、こうゆう環境から生まれる。
「苦痛」は、英知の父であり、愛情は母である。
そんな言葉があったなー。
2016年6月5日 21:38
北斗市郊外の山林で行方不明になっていた7歳児君、
見つかって、本当に良かった!!
4kmも離れた自衛隊の演習場にたどりつき、
鍵のかかっていない施設を発見し、何日間も、水を飲んで過ごしていたと言います。
車や人に、石を投げつけて「お仕置き」された・・・ということですが、
そんなお子様だからこそ、
こうして生き残るパワーみたいなものが、あったんだろうなー、なんて思います。
「名馬は、悍馬(かんば)より生ずる」
悍馬とは、気が荒く、制御しにくい暴れ馬。のこと。
「悍(かん)」という字には、気が強い、荒い。性格が、激しい。という意味があります。
・精悍(せいかん):顔つきや態度に、勇ましく鋭い気性が現れていること
・剽悍(ひょうかん):素早く、荒々しく、強いこと
・・・こんな熟語にも、あらわされています。ちなみに、訓読みすると「悍(おぞ)ましい」です・・・。
良く走る馬は、「悍」なる性質を持っていることが多い。。ということ。
この少年、うまく育てれば、きっと将来有望です!
今回の騒動。置き去りにする親父の「悍」なるDNAと育て方が、
子供のDNAにうけつがれ、きちんと作用しているという、この家族の顛末なんだろうな・・・。
周りに迷惑をかけたこと、嘘ついちゃったことは、ダメですけど。
でも、本当に無事で、良かった。。
長所と短所は、表裏一体。
「優しい」には、「優しい」の長所と短所。
「おとなしい」には、「おとなしい」の長所と短所。
「スボラ」には、「スボラ」の長所と短所。
「明るい」には、「明るい」の長所と短所。
「しっかり」には、「しっかり」の長所と短所。。。
そうゆう個性を、人様の役に立ち、
一人前以上に、稼ぐことができるようにしてゆくのが、人材育成なんだろうな。
2016年4月24日 21:41
司馬さんは、
日本人を知るうえで「武士」の存在も挙げています。
武士を「人間の芸術品」と呼んでいます。
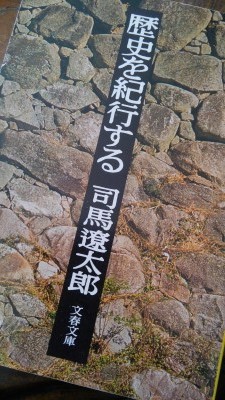
明治以降、飛躍的なスピードで先進国の仲間入りができた、その理由は
「汚職しなかったこと」
「公の意識が、横溢していたこと」
これを“痛々しいほどに清潔であった”と、表現しています。
このような高い倫理観は「武士」に由来している。
「名こそ、惜しけれ」という精神。
名を汚すようなことはしない。恥ずかしいことはするな。
これが、武士の価値観。
鎌倉時代、武士が初めて政権を獲得しました。
武士とは、貴族による律令制から、地方へ逃げ出して、
自ら農地を開墾した「百姓」が、武装化したもの。
素朴なリアリズムに裏打ちされた「百姓の政権・鎌倉幕府」により
自分の土地を認めてもらった恩義に対する
「名こそ、惜しけれ」の精神。
「名前を汚すような、恥ずかしいことをしてはならない」
「公のために、働く」
これも、日本人が日本人たる所以。
所属する会社や組織であり、
会社を信じて依頼をいただけるお客様であり、
身を置く業界であり、地域であり、
ひいては、日本全体へとつながる
「公」への奉仕と「名こそ惜しけれ」の精神。
司馬さんは、
書籍の中に「今でも、一部の清々しい日本人にみられる・・・」と記しています。
その一部に入っているだろうか。。
2016年4月23日 21:04

最近「価値観」について、考えています。
そもそも「日本人とは、何者なのか?」ということを、
司馬遼太郎さんの史観から、引用したい。
島国に生まれた日本人は、
「素晴らしいもの」は、他からやってくると信じていた。
古くは大陸から。明治維新以降は西洋から。
外への「好奇心」でもって、それを取り入れてきた。
神道も、仏教も、キリスト教も、受け入れる。それぞれの価値を認める。
「一神教的価値」を持たない民族である。
それは、元々、日本に「八百万(やおよろず)の神」という価値観があったからである。
自然物そのものを信仰し、山にも、岩にも、川にも、草木にも、神が宿るから、全ての神様を立てなければならない。
それによる「無思想」という思想で、
何でも柔軟に取り入れてきた。
外国からの文化を、取り入れるだけでなく、日本独自の形へと工夫を重ねる。
室町時代に代表される「枯山水」は、
外来の庭園文化の池や水を、砂で表現したもの。
住居は、書院造、床の間、障子、襖、畳。茶道も華道も、独自の文化となった。
つまりは、
「良いものを、柔軟に、外から興味と敬意を持って取り入れること」
「さらに良く使えるように、自分なりに工夫してアジャストさせること」
これが、日本人の特質である。
2016年4月8日 22:07

左が、セブンイレブンのドーナツ。
右が、ミスタードーナツのドーナツ。比較してみました。
主力商品「チョコ・オールドファッション」の場合。
セブンは93円、ミスドは140円。その価格差1.5倍。
サイズは、ミスドの方がひと回り以上大きい。
形状は、ミスドが上のほうが大きくなっていて(逆山型)、セブンは下に向かって広がっている(山型)
重量は、ほぼ同じ。(※実験サンプルでは、セブンのほうが少しだけ重かった)
食感と味は、ミスドはクリーミーで、軽いサクっとしたもの(年配層・子供層向けか?)。セブンはドッシリとした食感を重視。ザクっという食感(若年世代向けか?)
・チョコの量と味は、ほぼ同じ。
単純に商品そのものが、どちらが美味しいか?
どちらを食べたいか?と言われれば、
当初、まずくて食べられたものではなかったセブンのドーナツが、
品質面で追いついてきている。と判断せざるをえません。

ミスタードーナツも、品質を上げて、対抗策を打っています。
しかしながら、今年の3月末の決算発表で、
ミスタードーナツの売上は、約10%のマイナス。
ここ数年で一番悪い数字となっています。
クリーニング店は、ここから何を学び、何を実践すべきか・・・
そんなことを、業界紙「全国ドライ新聞」様の次回号に、
1面ぶち抜きで連載させていただいております。
是非、ご一読くださいませ。