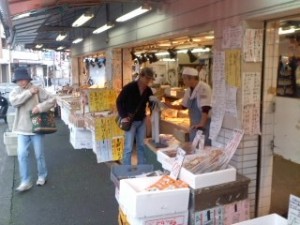2013年2月8日 14:03
クリーニング取次店で、単店でン千万円のコインランドリーを経営している人がいる。。。と聞き、
クライアントのご厚意により、訪問させていただきました!

写真の通り、
立地は、普通。
コイン機械の台数も、普通。
コイン機械の性能は・・・ちょっと古い。
でも、売上は、「繁盛店」と言われるコインランドリーの3倍以上の売上!!
その秘訣、、、
それは「素人発想で、行動する」のが、やっぱり最強だ。。。ということ。
業界の人が考えないようなことを、
お客様の目線で、平気でやってのけてしまっているのです。
ちなみに、
敷地内には「コイン精米機」もあり、これも、平均的な売上の3倍以上。
ここにも素人ならではの、ちょっとした工夫がありました!
工夫しながら、楽しみながら、売っている。。。
それが、伝わる空間でした。
こんなものまで売っていました!

なにーーぃっ!!壇蜜??
・・・蜂蜜かぁ・・・。
僕のアタマ、、おかしい??
いや、ほとんどの男子は、そう見えたに違いない!!
どーでしょう??(笑)
2013年2月2日 20:45

鹿児島の翌日は、北海道へ。
鹿児島では、コートを着ていたら汗ばんでいたのですが、
北海道では、コート1枚では、凍えてしまいそう。
今年は、雪が多いそうです。
1日で南の端から北の端へ。
こんなことは、滅多にないのですが。。。
おかげさまで、1月~2月は、スケジュール、パンパンです。
こうして移動することは、大変ですが、
必勝を得るための「戦略・戦術」は、
「現場」を見てからでなければ、作ることはできませんので、、、仕方ありません。
それは、
「ただ人から聞いたこと」なのか?
「自分の目で見て、体験して、感じたこと」なのか?
現場の道理にあわない指示・命令ほど、無駄なものはありません。
創業から3年目。。。
枯れてしまうどころか、どんどん増えてゆくご支援先に、
原理原則を大切に臨まなければ、、、と、心を新たにしています。
今年が「厄年」で、去年が「前厄」だった。。。と、つい最近、知りましたー(涙)
気を引き締めて、進んでゆきます!!
2013年1月9日 8:25
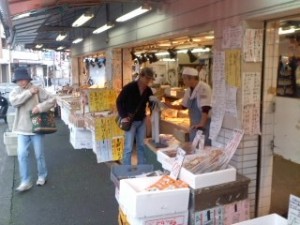
全国を出張で回っていると、
「おおっ!」という繁盛店に、偶然、巡りあうことがあります。
この魚屋さん・・・見る人がみれば、
ひとめでわかる「繁盛店」!!
良く「これは本物だ・・・」なんて、表現がありますが、
正直言って「あとづけで条件付けして定義した」感があり、あまりピンときませんでした。
この魚屋さんを見て、思います。。。
「本気」こそが、「本物」なんだ!!

ご覧ください。
お店の横の壁面が・・・手書きチラシだらけ!!
このお店のお母さんが、お客様のために「魚のレシピ」を書き綴ったものだそうです。
見事な「本気」っぷり!!
ギョギョギョ~。
2013年1月7日 7:45
新年早々、魂に火がついた!!
年末、何者かによって、壁にペンキが、ぶっかけられていました。。。
初仕事は、正月休みに運動がてら、ペンキ除去作業♪♪♪ って、
お釈迦様のような穏やかな表情で、楽しみながらペンキを消しつつ、
心中は、「ゼッタイに許さん・・・」「このまま終わらせん・・・」と、不動明王のような怒りのパワーに満ち溢れています。
こうゆうことがあると、闘志とアイデア、ヤル気が、ギンギンに活性化されます!!
すでに、これを契機にもっと稼げる方法&犯人が一生ヘコむ方法を、キッチリ仕込みました。
(楽しみ、楽しみ・・・ウッキッキ~)
経営者、いや・・・男は「反発係数」が強くなければ、やっていけません。
自然界において、2つの物体が衝突したときには、反発係数が1より大きくなることはありません。
しかし、男は、好ましからざる事態に即して、
それを1以上にして「はねのける」パワーが、どれほど強いかによって、生きぬくチカラが決まるのです。
「やられたら、倍にしてやりかえす」
それは、見栄えのする派手な一瞬の反発力や、子供じみた反発力では、決してありません。
社会的に認められる堂々たる「大人の反発力」で勝負するのです。
現時点では、どう逆立ちしても、かなわないことやどうしようもないことだってあります。
そうゆうときは「5年かけても、2発殴り返せ!」こう教えてもらいました。
自分にふりかかるマイナスを、如何にプラスに持ってゆくか?
辛抱強く、ガマンして、叩かれ続けていても、誰も助けてくれないのです。

業者さんやスタッフに、ペンキ消し作業をまかせるという選択肢もありですが・・・
ここは「零細企業のオヤジ魂」を磨き「闘争心」を刻み込むため、自分でやる!!!
たぶん、サラリーマン・コンサルタント時代は、こんなことしなかった。。。
経営者の心は「アタマ」で理解した気になっていただけ。
「独立してから、コンサルティングにキレが増してきましたね」そう言われることがあるのは、
こうしてクライアント先の社長と同様の体験ができていることも、大きな要因だと思います。
2012年12月6日 9:04
船が海にいると、船底には「かきがら」がくっつきます。
ドッグに上げられた船を見ると、
普段、海の中に沈んでいる船底部分に、フジツボをはじめとする貝殻がビッシリとついている、
あれが「かきがら」です。
「かきがら」が船底につくとどうなるか? ・・・2~3割も船の速力が落ちてしまいます。
そうすると、、、
漁船の場合なら、魚を捕る。
戦艦の場合なら、敵を攻撃する。
タンカーや客船の場合なら、物や人を運ぶ。
本来の「目的」を達成するために重大な支障をきたしてしまいます。
だから定期的に「かきがら落とし」をして、船底をキレイにしておく必要があるのです。
人の頭の中にも、長い人生の中で「かきがら」がつきます。
「業績を上げ、自分が食べ、自分の周りを幸せにする」という人生の目的を達成するために、重大な支障となっているのです。
この「かきがら」を「固定概念」と呼びます。
頭の中に「かきがら」(固定概念)が存在してしまうこと自体は、悪いことではありません。
むしろ、その方が自然だと言えます。
一番怖いのは、自分自身がどっぷりと若い頃の成功体験や、自分流のやり方、楽な方法、
景気が良かった頃のやり方、業界の慣習に浸りきってしまい、
「これでいい!」「これがいい!」と、
自分の頭の中にかきがら(固定概念)がビッシリこびりついていることにさえ、気づかないでいることです。
その点、素人は、知識や技術がないかわりに、「かきがら」もないから、
必要で合理的だと思うことは、どしどし採用して実行します。
異業種から飛び込んできた人が、各業界で良く成功するのは、
この辺りに理由があるのだろうと思います。
業績を上げようと思えば、
他力本願で景気の上向きを待つよりも、頭の中の「かきがら落とし」からはじめることが先決です。
今日は、仕事モードで、マジメにブログ書いたぞー!