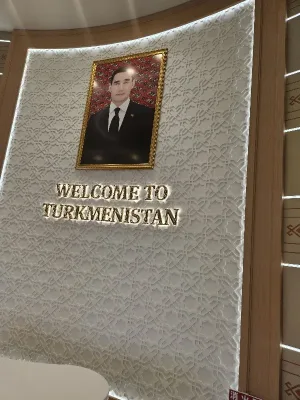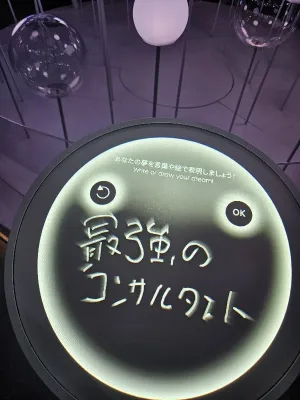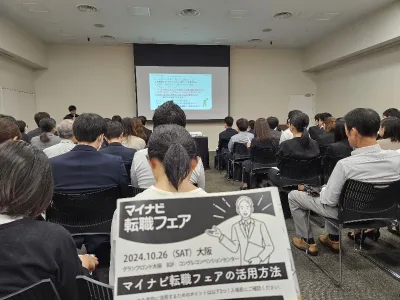2025年10月19日 19:59
トルクメニスタンは、独立パビリオンで出展。
マイナーですが独裁国家。「中央アジアの北朝鮮」とも呼ばれ、
特別な許可がないと渡航できないそうです。
入口で迎えるのは、この写真。
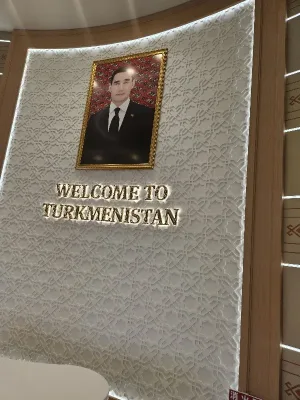
「誰ですか?」と尋ねると、
ブスっとしたコンパニオンが、
ブスっと「大統領です」と教えてくれました。
(ん??あまり、愛されてないのかな?)と、邪推してしまいます。
レーニン、スターリン、毛沢東、金正日、ヒトラー、
戦時中の昭和天皇、ヤクザの親分、宗教団体の教祖・・・
自分の写真を、
自分の影響範囲に掲げさせるのは、
心理的支配をもくろむ独裁組織の特長です。
そして、非合理的社会を作っている不安の裏返しでもあります。
(お、、そう言えば、某FCチェーンでも・・・笑)

そして展示は、とても鮮やかな「没入型」
外部にも大動画スクリーンを備え、国威を誇示していました。

↑この「外観に大動画」スタイルは、アメリカとトルクメニスタンのみ。
万博で、はじめて知った国でした。
2025年9月14日 19:01
シンガポール館には
「あなたの夢を言葉や絵で表現してみましょう」書いてください。
というコーナーがあります。
私は、迷うことなく、こう書きました。
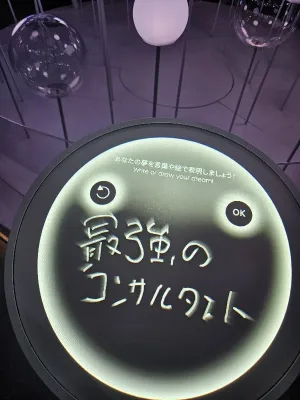
「最強のコンサルタント」
追っても、追っても、届くことのない。でも、必ず実現したいこと。
そして、2階に上がると、
天井に広がる巨大スクリーンのなかに、
先ほど書いた「夢」が、ふわーっと出てくるのです。
何度か、色んなところに、みんなのものと一緒に出てきます。

・360度、巨大スクリーン
・自分だけのオリジナル
シンガポール館は、人気パビリオンの条件2つを融合しています。

・・・・
「平和」「笑顔」「健康」「家族」「幸せ」「楽しく」「仲良し」
そうゆうワードが、大多数を占めています。
一般的には、そうゆうことなんですよね。
自分が普通ではない認識の持ち主であることは、理解できました。
ちょっと毛色が異なっています。
一緒に来た友人から「お前、ルフィか!」
(海賊王にオレはなる!)みたいだ。と言われました。
確かに、子供のようです。
夢を追い続けています。
自分の生涯を通して実現させたい価値・使命を自覚し、志に生きています。
みんなの夢を一覧的に見させてもらう。って、面白いです。
ずーっと見ていても、飽きません。
2025年7月6日 21:58
転職フェアでは、
転職者向け・ノウハウセミナーも併催されていましたので、
これも、転職者のふりをして潜入。受講してきました。
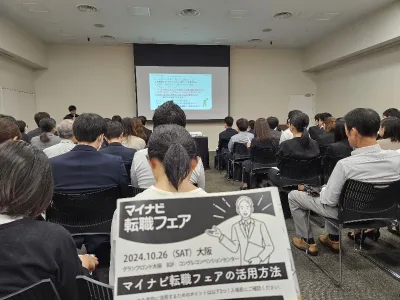
採用や転職のコンサルタントの方が講演しておられました。
以下、主な内容です。
↓↓
現在は、有効求人倍率2.86倍、空前の売り手市場(雇用される側に有利)である。
しかし、職種によって倍率に大きな開きがある。
ITエンジニア12倍、事務は0.65倍である。
昨年の転職者のうち年収アップする人35%は、ダウンする人が35%
同一職種なら上がる。業界と職種を変えると下がる。という傾向がある。
志望企業を事前に調べてから、面接に向かうこと。
自分の転職理由は何か?
叶えたい希望を「ひとつ」に絞ることが大事。
収入?勤務時間?休日?勤務地?職種?仕事内容?環境?
自分の「やりたいこと」と、会社が「やらせたいこと」が違うことがある。
WEBの転職者の口コミをどこまで信じるか?
⇒あくまで参考に予測を立てる材料にする。鵜呑みにはせず、確かめる。
フェアのブースでは、出会いと偶然を大事にする。
ブースでは、その会社の人柄を見るとよい。
「違うなー」という感覚も大事にする。それを本命での志望動機に使うことができる。
「志望動機」を聞いてくる採用担当者に対して、
「別に御社じゃなくてもいいんです」論争がネットで話題になった。
でも、志望動機は、しっかり作るほうが良い。
ちなみに、うまい面接担当者は「志望動機は何ですか?」とは聞かない。
記憶は曖昧になるから、すぐ行動するのが良い。
「袖触れ合うも何かのご縁」
合否のメールやお誘いのメールが来たら、必ず返しておくこと。無視はNG。
というのも、後々、仕事やプライベートで、どこかで、会うことがある。
面接していた人が、営業に来たり、商談相手だったりすることが、
これまで何度もある。
当たり前だけど、、
履歴書の日付のチェックをすること=履歴書の使いまわしも良いが注意しておいてください。
↑↑
・・・・
みんな真面目に受けているなあ。と実感しました。
セミナーまで受ける真面目な転職者はどんな年齢でどんな層か?
転職者へ効くフレーズは何か?
転職者からどうやって「調べられる」ようにしておくのか?
どんな仕掛けを作り、待ち受けるか?
面接内容は、どうするか??
転職者が勉強していること、思考・行動パターンも、
頭に入れておくために、セミナーにも参加しました。
売上アップのマーケティングでは、
お客様・競合相手・自社。
これらの現状を正確に知っておくこと。
それに基づいた対策を立てること。
転職者の採用についても、同じです。
転職者・競合相手・自社。
この力関係を把握することがスタート地点です。
2025年4月26日 19:57
「組織づくりの要諦は、壊すことにあり」
以前ブログでご紹介させていただいた船井総研の元社長・本告正さんに、
https://cleaning-keiei.com/nakanishi/2023/12/17/
社長室に「ご招待」いただき(=お呼び出しをくらい?笑)
お話したとき、教えていただいた言葉です。
「どんなに成功していても、うまく行ってても、組織は3年に1度は、必ず壊すものなんだ」
「新しい組織がうまく機能するかどうか、とか、人事がどうだ。ということは、たいして大きな問題ではない」
「定期的にバラバラに壊すこと自体が、大切なんだ」
私が入社して数年目のとき、大きな組織変更があって、
おそらく「不満半分」で、尋ねたのだと思います。
やっと会社にも人にも仕事にも慣れてきたのに・・・業績も順調なのに・・・なぜ??
という思いから。
(ふーーん、そんなものなのか)
(まあ、確かに、銀行とか大企業は、3年に一度は、部署移動するってゆうしなー)
(しっかし、テキトーだなあ、そんな感じでええんかいな??)
当時は、このくらいにしか、考えていませんでした。
でも、前述の「動的平衡」により、説明がつきます。
「生命は、絶えず自らを壊しながら、作り直すことでバランスを保っている」
個体が集まっている人間社会も生命体である。会社も生命体である。
人間と他の生物も、地球全体も、ひとつの生命体と言うことができる。
実際、伸びる会社ほど、
一見、非情に思える大胆な人事をします。
店舗リーダーに、突然、工場長をさせる。工場長が、店舗責任者になる。
居住地から、遠くの拠点でも、おかまいなく単身赴任させる。などなど。
伸びない会社は、ずーっと人事が固定です。
社長も、幹部も、リーダーも、同じところにいます。
※
日本の官僚組織とか、定期的に「壊す」といいんですよね。きっと。
部署や編成自体を、大きく入れ替える。
簡単に実施するなら、財務省の課長が、いきなり、文科省の課長になる。入れ替わる。とか。ね。
そうすれば、国という生命体も健康になると思います。
2025年4月20日 19:42
生物学者の福岡伸一氏が提唱する概念です。
「生命は、絶えず自らを壊しながら、作り直すことでバランスを保っている」
福岡さんは、優しそうなお顔と語り口と裏腹に、
こんな実験を、マウスに施した。
マウスのなかのひとつの遺伝子を無効化する。
つまり、意図的に身体の異変を作りだそうとする。
しかし、元気に生き続ける。
遺伝子は、大きなシステムのなかの一部なので、
すぐマウス本体に大きな異常をきたす前に、足りない遺伝子をバックアップしたり、
補完しあう仕組みが働き、
マウスのなかに「新しい平衡=バランス」が立ち上がる。
機械の場合、部品が壊れると、やがて全体に影響が及ぶ。
しかし、生命の場合、ひとつ取り除いても、大丈夫なようにできている。
自助的に全体に影響が及ばないようになっている。
生物は「動的な仕組みとして統合的な存在」なのです。
絶え間ない流れの中で分解、合成がバランスをとっていることを「動的平衡」と呼ぶ。
生命の本質は、
遺伝子や細胞といった個別の要素にあるのではなく、
要素と要素の関係性、それらの「あいだ」で起きる相互作用にある。
そこに生命が宿っている。との結論にいたる。
会社やチームに置き替えて言えば、下記のようになる。
組織の本質は、個人や役割といった個別の要素にあるのではなく、
個人と個人。役割と役割。の関係性、それらの「あいだ」で起きる相互作用にある。
そこに組織の生命が宿っている。
モノではなく、そこで織り成しあうコトにある。
組織では、日頃から、色んな構成員同士の「相互作用」「あいだ」の機会の「量と質」を、大切にしておくと良い。
1つのピースが抜けた後の「新しい平衡の立ち上がり」がスムーズになります。

生命は「壊しながら、作ること」で、バランスを保つ。
ダルビッシュが抜けたあとも、チームが勝てることも、動的平衡のひとつです。