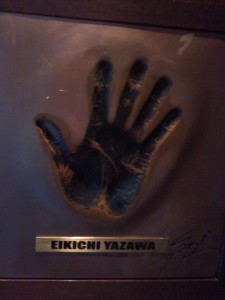2013年2月1日 22:43

今日は、鹿児島です。
桜島は、毎日、噴火するそうです。
火山灰で空はかすみ、道行く車は白く灰が積もっています。
私が知っている鹿児島の経営者の皆さんに共通していること。
それは、どこか「西郷隆盛」を感じさせる雰囲気があることです。
今日、お会いした社長・幹部の方にも「西郷」を感じました。
なぜでしょう??
社長や幹部に、特に「我が、現代の西郷たらん・・・」という雰囲気が、自然と醸しだされているのです。
「薩摩の士風」
それが「経営者」という立場の人々には、特に色濃く伝承されていると思います。
近代日本の礎を作った明治維新。
薩摩(鹿児島県)においては、「士農工商」のうち、維新の原動力となったのは「士」の身分の人たちでした。
しかし、一般的に維新とは、
長州(山口県)や、土佐(高知県)に代表されるように、
「武士の時代」に「武士以外の志士」が終止符をうったものでした。
中央では、腐ってしまった戦国以来の「武士」の姿が、
地理的にも遠く「隔離」されていた薩摩では、きっちりと教育され、残り続けていた。
武士が武士として、あり続けた地域。。。それが薩摩です。
封建社会のトップに立つ「武士」の在り方が、
資本主義社会のトップに立つ「経営者」の在り方に、引き継がれている。
そのように思います。
言葉よりも
人格や行動を重んずる。
一対一の戦い、
それも「一の太刀・・・相手への一発目の働きかけ」に集中する。
戦国より続く「薩摩の士風」を身近に感じることができる、、、
感謝です。
2012年12月27日 8:19

「えーちゃん」コール・・・やってきました~。
今年も、なかなか頑張った自分へのご褒美です。
今年のコンサートで、一番感じたこと・・・
それは、矢沢永吉さんの笑顔が、とってもステキなこと!
「今の俺は、あんなに素敵な笑顔で、仕事ができているだろうか??」
笑顔にも、色んな種類の笑顔があります。
観客のことを考え、精一杯に音楽を作って、
それに、満足して喜んでもらっていることを感じたときの「共感と充実」の笑顔でしょう。
60歳を過ぎても、あんな笑顔で仕事をしている男になるぞ!!
そう決めた1日でした。えーちゃんから「宿題」をもらいました。
NHKの特集でのインタビューより、、
「NO1であり続けることができる理由」を聞かれ、
「それは、臆病だからじゃないですかね」と答えていました!
じゃーーーん!!

タオルも一流ですよ・・・
「投げる専用」なのに、そのへんの「洗う専用」が勝てないくらい、良い生地で作られています(笑)
コンサートが終わったら、すぐにもう一度、DVDを見る!!
もこみち君の「追い・オリーブオイル」ならぬ「追い・矢沢永吉」。
YAZAWA効果倍増!!
ヨロシク!
2012年12月22日 0:23

ご支援先への訪問の途中・・・
初代総理大臣・伊藤博文の墓所がありました。
とっても大きな敷地にあります。
さて、今の政治や「第96代目」となる総理大臣に、何とメッセージを送るのか・・・。
幕末から明治を生き抜いた政治家のなかでも、
明るくおおらかで、豪快なイメージの強い伊藤博文。
17歳で、吉田松陰の「松下村塾」の門下生となり、歴史の表舞台に登場します。
松陰は、当時の伊藤博文のことを、こう評しています。
「才劣り、学幼きも、質直にして華なし、僕すこぶるこれを愛す」
「周旋(政治)の才あり」
松陰が、門下生の長所を見つけ、伸ばしてゆく眼は、さすがと言うべきです。
伊藤博文が、低い身分で「才劣り、学幼き」ながら、
大任を果たす人物となりえたのは、きっとその性格と行動力にあります。
「兄貴分の天才」高杉晋作、「悪友」井上馨とともに、
刑死した吉田松陰の改葬を幕府に抗い行う、英国領事館を焼き討ちする、
寝巻と辞書だけでイギリスへの密留学を敢行する、
わずか70人から決起し藩と戦い統一し、長州征伐に来た幕府軍とも戦う・・・。
まあ本当に、良く死なずに暴れまわったな・・・という青春時代。
「どんなヤツとつるむのか?」は、人生にとって、本当に大事です!!
そして、その後の伊藤の人生を見れば、
わずか1年の「イギリス留学」で、海外の国体を知り、英語が話せるようになっていたことも、
「ブレイクの種」となっています。
私が思うに、伊藤博文の「ブレイクの種」は、「高杉晋作」と「イギリス留学」。
さあ、私たちにとっての「種」は、何でしょう?
チャンスを見逃さず、生きてゆきましょう!
2012年11月22日 8:38
この政党にコンサルティングを頼まれたら、
どう戦うだろうか?
この議員を当選させるためには、
どうアドバイスするだろうか?
選挙のときには、毎回、そんなことを考えながら、ニュースや新聞を見ています。
コンサルタントの職業病。。いや必須条件なのかもしれません。
とにかく頼まれたら、絶対に勝たせる!
ケンカに強くなければ、コンサルタントはやっていけません。
大事なことは、「論点」をどう見せるか?
たとえば、
小泉首相の「郵政民営化。YESか、NOか」
民主党の「政権交代。YESか、NOか」
大衆に訴えかけるには、多くの人が納得できる、わかりやすい論点を設定して、
「YESか、NOか」で迫ることが、ポイントなのです。
正しいのか、間違っているのかは、別として。
これは、売上アップ・マーケティングでも定石です。
今回の民主党・・・苦戦はまぬがれないでしょう。
野田総理は解散の演説で「前に進むか、後ろに戻るか」のフレーズを繰り返し、
「論点」を設定しようとしていました。
「前=民主党か、後=自民党、どっち?」ということなのでしょうが、
これは、いわゆる「第三極」の躍進を助ける「論点」です。
選挙民は「どちらもイヤだ、誰か新しい人を・・・」となる論点です。
2012年11月3日 8:14

すみませんね!
永ちゃんブログ・・・第二弾です。
私が16年間、サラリーマンでありながら、
「経営者マインド」を持って仕事をしてきたのは、永ちゃんの影響もあるかもしれません。
好きでやっている職業が、アーティスト。
それでいて、ものすごく地道に「中小企業のオヤジ」の進む道を歩いている・・・
そこが他のミュージシャンと永ちゃんの決定的な違いです。その「生き様」に共感できるのです。
詳しくは書きませんが、、、矢沢永吉さんは、
音楽業界や芸能界、マスコミという「長いモノ」や「権威」に媚びず、
堂々と正論を通し「自分のやりたいこと」と「お客様の共感」を一致できている
「一人の熱い事業家」でもあるのです。
そして、仕事=音楽やステージに対して、本当に真面目です。
徹底的に「最高のモノ」に、こだわっています。
ガイジン・バックバンドも「それが世界最高だから」そうしたそうです。
ここ「ダイヤモンド・ムーン」で食べた、パスタセットのナポリタンまで
・・・史上最高に美味しいのです。ひいき目なしで。
味もボリュームも、食べたことのないナポリタンでした!
「時代とか人のせいじゃない。どんな時代でも、やるヤツはやる。やらないヤツはやらない。」
「じゃあ、オマエも、やれば?」
「スタートを切っているかどうかの問題じゃないの?」
と、永ちゃんが、いつも心の中で、話しかけてくるのです。
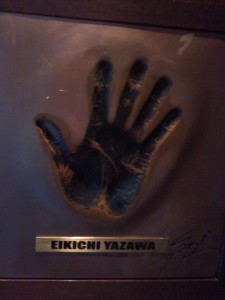
おっ!!出口にこんなものが~。

(永ちゃんと握手しちゃった・・・)
(しかも、ぴったりおんなじ大きさ!!)
フフーン♪♡
ヨロシク。