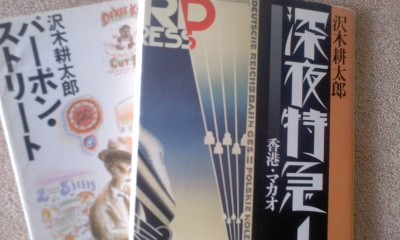2015年5月5日 6:34
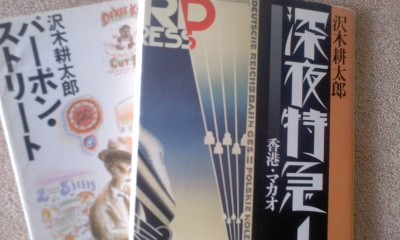
「ゴールデンウィークは、本を読もう!」と、決心するも、
新しい本を買って、読むほどの気力と時間は、残されておらず・・・
昔、読んだ本のなかで、
捨てずに置いてある「マイ・セレクション」を、
引きずり出して、気楽に読むことに。
人生の放浪癖・・・というか、
「俺は、リュックひとつで、どこでも楽しく、生きてゆける・・・」と、
心のどこかで思っている(悪しき?)自分を作っている一要因が、コレ。
・・・沢木耕太郎さんの本。
毛が生え始めてから、
身長が止まるくらいまでのうち=10代前半~20代前半、
いわゆる思春期に出会った人や、本は、
人格形成に、大きな影響を与えるみたいです。
2015年5月3日 23:29
先日のブログの続き。
「装置産業」と「ソフト産業」という、
両極端な事業の体質を、1つの会社で、併せ持つようにすれば、
盤石の会社が、出来上がってゆきます。
視点を変えれば、「見込み生産」と「受注生産」にも、当てはまります。
事業には、2つの体質があります。
自社で商品を作り、値段を決める「見込み生産・事業」と、
相手の要望に応じて、商品を作る「受注生産・事業」です。
「見込み生産」は、
ひとつの商品を、まとめて作り、それを販売してゆく生産方法。
大量生産によるコストダウンで、1個ごとの利益は、大きくとれます。
しかし、販売は安定しません。売れ残った在庫のリスクもあります。
ビールやジュース、テレビ、自動車・・・などは、見込み生産による商品です。
「受注生産」は、
お客様の要望に従って、設計し、商品を生産するスタイル。
顧客との継続的な取引である場合が多いので、売上は安定します。
しかし、人手がかかり、下請け・請負型であることから、利益は薄くなります。
印刷業や、建設業、製造業などが、受注生産の事業です。
これも、先日のブログ内容と、同じく、
「見込み生産」の会社は、「受注生産」の要素を、併せ持つと、儲かる。
「受注生産」の会社は、「見込み生産」の要素を、併せ持つと、儲かる。
「個人需要」と「法人需要」の関係も、
「店舗販売」と「訪問販売」「WEB販売」の関係も、同じ。
ここで、ちょっとしたポイントがあります。
それは「最終到達系の両極端を、同時に持つ」ということ。
中途半端な「あいのこ」「中間系」では、ダメなんです。
最終到達系とは、
そのものだけは、絶対に消えない、そのものだけで存続可能なものです。
さらに、余談・・・
お会いする経営者や幹部も、同じだな~、と感じています。
優秀な経営者・幹部さんは、
「大胆」と「臆病」。
「温情」と「冷酷」。
「ケチ」と「太っ腹」。。
性格の中に、両極端が、同居しています。
2015年5月1日 7:42

隠れ家カフェにて・・・経営原則について、真面目にまとめてみました。
設備や、生産ライン、施設ありきで、
利益を生み出す産業のことを、「装置産業」と呼びます。
工場系の製造業や、
ホテルや、パチンコ店、結婚式場などが、代表例。
クリーニング業界も、装置産業の性質が、強い業界です。
「装置産業は、儲からない・・・」
装置産業に関わる、経営者さんは、こんな声を上げます。
設備投資の金額が大きく、
かけたお金が戻ってくるのに、何十年とかかってしまうのが、その理由です。
そして、そのうちライバルが、巨大な資本で出現し、
売上・利益を奪われる・・・。
借金返済だけは、変わらない。
一方で、「装置産業」の対極にある、
「ソフト産業」の経営者たちも、「大変だ・・」と、こぼしています。
代表例は、WEB制作会社、アプリ開発会社、
デザイナー等。コンサルタント業も、ソフト産業。
参入障壁が少ないので、どんどん新規参入者が相次ぎ、競争にさらされる。
時流、流行についてゆけなくなると、全く売れない。
人に頼る部分が大きいので、安定しない。
一般的な特長をまとめてみると、
「装置産業」は、
在庫や投資等、資本の負担が大きく、回収に時間がかかる。
しかし、継続性は高く、半自動的に利益を生み出し続けてくれる。
「ソフト産業」は、
資本負担が少なく、即、キャッシュを生み出すことができる。
しかし、何年間も継続的に、それを続けることは、至難の業。
で、私が、色んな会社を見てきての結論。
「装置産業」の会社が、
「ソフト力」に優れていると、とても、儲かるようになる。
「ソフト産業」の会社が、
「装置力」を持つようになると、とても、儲かるようになる。
「性格の異なる事業特性の両端を併せ持つこと」
これは、強い会社づくりのコツなのです。
2015年4月19日 7:50
「創業」とは、新しく事業を始めること。
「守成」とは、築き上げたものを守り続けていくこと。
つまり、新しく事業を始めることは容易だが、
築き上げてきたことを、衰えないよう守っていくことは難しいということ。
出店して、相手を攻めたてるほうが、簡単で、
出店されて、相手を迎え撃つほうが、難しい。
クリーニング店の現場、会社の運営でも、まったく同じですね。
例を挙げてみると・・・。
新店舗の営業時間や定休日を決め、
それに沿って、新スタッフを募集して、教育してゆくほうが、簡単。
ライバル相手を迎え撃つために、
今ある既存店の営業時間を、1時間、延長しよう!とか、定休日をなくそう!と、
現状を変えるほうが、困難。手こずる。
では、「守成」のため、具体的に、どうすべきか?
第一に、一度「ぶち壊す」という覚悟とパワー。
第二に、仕事とは、自分本位でなく、市場本位であることを理解し、柔軟に変化できる人材力。
こんな要素が、必要となります。
だから「創業」以上に、攻めなければ「守成」は、うまくいかない。
メモ・・・
「創業は易く、守成は難し」
この言葉は、貞観政要(じょうがんせいよう)という中国の書物の一文。
善政を布いたといわれる、唐の太宗と臣下のやりとりを、まとめたもの。
君臣の模範となる言行録だそうです!!
2015年4月15日 22:40
大阪駅と直結の商業施設。
販売不振で閉鎖していた伊勢丹が「ルクア1100イーレ」として、リニューアルオープンしました。
地下2階、地上10階。大阪駅周辺でも、最大規模のフロア面積。
すぐ隣の専門店ビル「ルクア」が、成功しているので、
それを、さらに拡大したらええんや!(2匹目のドジョウ)で、
ルクア同様、評判の専門店を、いっぱい集めてリニューアルした。
要は、そうゆうコンセプトのリニューアルです。
ちなみに、、、
百貨店の「ひゃく・100」と、
専門店の1000「せん・1000」の融合という意味で、「1100・イーレ」。
オープン当日の19時ごろ、仕事帰りに、寄ってみました!
と言っても、ルクア1100のオープンの影響を受けるであろう、
最も近い商業施設が、どんな手を打っているのか、どんな状況なのか?が、
コンサルタントの主たる目的。
イーレの店内は、ささーっと見る。
後で、いつでも、見ることができます。
しかし、ライバルの商業施設のオープン当日の状況は、
この日しか、見ることができません。

大丸百貨店の4階・婦人服フロア、がらーん。

グランフロント南館の3階、繁盛していると言われているグランフロントすら、この状況。
当日のライバル店対策は・・・、ほとんど打っていません。
大企業とは、そんなものなんでしょうか?
中小企業では、考えられません。
「相乗効果で、いずれウチも儲かるから・・・」という判断なのかな?
裏で、紳士協定が結ばれているのかな?
イーレの運営主体は「JR伊勢丹」なので、
JRの駅直結の2社としては、JRに遠慮してのことだったのでしょうか?
あらゆる仮説が思い浮かびます。
コンサルタントのアタマのなかには、
この逆風を活かして、
自分も儲けちゃう戦術が、グルグル巡っています。
・・・・
大塚家具だって・・・実に、オイシイ!
この逆風は、チャンスですよね!