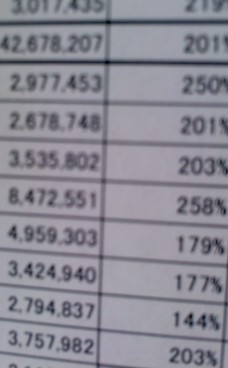2014年4月19日 16:53
人材育成に関するセミナーを、
クリーニング業界ではない他業種のセミナーで開催しました。

メイン講師は、弊社・コンサルタントの玉川治宏。
とても、わかりやすく、
自分自身にとっても、勉強になる内容でしたので、
メモした内容の一部を、ご紹介します!
1
中小・零細企業に、優秀な人は、なかなか入社しない。
普通レベルの人材を、戦力化する方法が、ある。
2
人材育成に成功している会社の特長のひとつ。
社長自らが、社内で勉強会の講師をしている。
外部講師だけに、まかせっきりにしない。
3
経営学者・ドラッガーは
「マネージャー(管理者)」を、このように定義する。
「成果」に責任を持つ人。
その成果のために、専門家を束ねて、貢献する人。
「管理」がマネージャーの役割であった時代は、終わった。
4
一般社員と管理職の違いは?
社長と管理職の違いは?
管理職のやりがいとは、何か?
社長に、期待されている管理職の役割とは?
どう認識しているのかを、再確認せよ。
5
人材育成の根底にある思想は
「育てる」のではなく「育つ環境」を作ることにある。
自分が抜かれるかもしれない・・・というリスクを排除する。。。他、
10のチェックポイントがある。
6
モチベーションは、上司によって高められるものか?
それは「高める」のではなく、「高まる」もの。
上司は、モチベーションを上げようとしなくていいから、
まず、下げる言動を止めよ!
7
販売力のある会社は、
「ロールプレイング」を社内で実施している。
8
「自分で答えを出させる道筋」を、
計画的に、社内に定着させる。
・・・・30個くらい、メモしました!!
うちの会社でも、、、
できていないこと、たっくさんだーー(泣)
でも、今から、やったら、強い会社になるぞ!
よしっ!
2014年4月15日 16:22
STAP細胞・小保方晴子さんの記者会見で
出てきた「再現性」という言葉。
あるテーマに対して、
第三者がやって、同じ成果が得られる性質や度合いのことを、再現性と呼びます。
だれが、
いつ、
どこで、
どのように、、、という
各種の要件が変化したとき、その成果に、
どれほどのばらつきがあるのか?という点に至るまで、
数字と事例で証明することが、再現性です。
我々が、コンサルティングしている
マーケティングの世界でも、この「再現性」が、とても重要なのです。
「ある会社が成功したことを、別の会社が実行して、同様に成功するのか?」
これが、マーケティングの再現性=ノウハウ。
マーケティングは、科学です。
たとえば、
あるクリーニング店が「ポスティング・チラシ」で、集客に成功している。
60名以上の新規集客がある。
これは、事実。
ところが、
これを「こんなポスティング・チラシをやれば、60名の新規客!」と、
セミナーの場で発表する、、、ということを、当社は、しません。
なぜなら、、
それはある条件での「個別事象」にすぎないからです。
他のクリーニング店が、同じことをやって、60名集まるかどうか、
成功するかどうか、この時点では、わかりません。
異なる条件のもとでの「再現性」が、未確定なうちは、
ノウハウであるとは言えません。
また、ノウハウと呼べるレベルに昇華するまで、
発表すべきではないと考えています。
それぞれのクリーニング店で、
地域性や条件は、まったく異なります。
各地で、何度も、実行と検証を繰り返した結果、
成功のための条件を数字でつかみ、整理したうえで、
私たちは、こうお伝えします。
「御社が今、成功した他社と同様の“ポスティング・チラシ”をやれば、
現状、それぞれの条件・要素が、こうなっていますので、
15名~25名くらいの新規集客と、予測できます。」
「もし、60名の新規顧客を集めたければ、
各種の条件・要素を、
このような方法で、改善してゆくことが、必要です。
それに伴う、時間とコストは、このくらいかかります」と。
さてさて・・・
これから「ノウハウ」となるであろう、
こーんな個別事象の数字が、
日々、集まってきています。
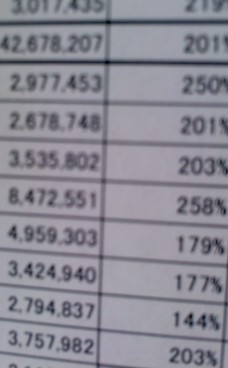
2013年12月3日 22:09

弘前城の紅葉です。
戦争には向きませんが、治世には向いてそうなお城です。
ある程度、戦乱が収まったころに作られたのでしょう。
平和な時代の香りがします。まるで京都のお寺のよう。
さて、
日本には、歴史による商圏の違いが存在している・・・ということに関連して、
少しだけ、コンサルタントの商圏の見方について、まとめてみました。
商圏とは、「商売の影響力を及ぼせる範囲」のこと。
出店する時や、チラシを配布する時には、
この「商圏」を、慎重に見極めなければなりません。
商圏には「分断要因」がある。。。ということは、ビジネス書には、良く書かれています。
大きな川や海・山、道路、線路など。
しかし、これは、いわゆる「常識的な一般論」。
商圏に「拡大要因」があることは、あまり知られていません。
これは、地図上で見るだけでなく、
実際に現場で実務をしながら、数字で検証を繰り返して、初めて見えてくることです。
たとえば、大きな川があれば、分断されます。
橋のあるところまで行かなければならないからです。
しかしながら、橋のたもとのエリアには、ギュっと、人が集まってきますので、
このスポットは、商圏を広げてくれます。
線路と踏切に関しても同じことが言えます。
海には人が住んでいませんので、当然、分断要因です。
しかし、海沿いに一本しかない道は、商圏の拡大要因なのです。
その地域に住む人は「必ずそこを通らなけれなばならない」ので、
足元の商圏以上に、商圏が広がります。
大きな道路も、分断されます。車が多く、渡るのに時間がかかるからです。
しかしながら、道路沿いには、商圏が広がってゆきます。
道路に沿ってお客様が移動していますので、
住宅地から道一本で来店できる立地は、商圏を広げてくれます。
また、人は、人口の少ない地域から、人口が多い地域へと流れます。
商業施設の面積が大きいエリアに向かっても流れてゆきます。
クリーニング店を使うお客様は「田舎に向かって、くだって買う」という購買行動を起こしにくいのです。
専門性の高い商品を扱ったり、品揃えが充実していたり、
店の規模が大きければ、商圏が拡大します。
「あー、またあの無愛想な店員が待っているのかな~」
「何でも押し売りしてくる店員がいるぞ・・・」
これ、商圏の「心理的」分断要因。
「今日は、笑顔の素敵なあのスタッフに会えるかな~」
こちらは、商圏の拡大要因ですね。
2013年11月16日 7:10
先日のブログに追記があります。
スタッフ数10名くらいまでの「小規模な繁盛店」
「家業的な形態といえる繁盛店」の働き方をまとめてみます。
1.店は年中無休、営業時間は早朝から深夜まで。
2.働くこと、体を動かすこと、労力を惜しまない。体で稼ぐ、商売は体が資本と考える。
3.仕事(=商売)と個人生活の間に区切りがない、けじめがない。
4.お客様が店に来てくれている間は、店を開けておく。
お客様が起きている間は、自分も起きている。
考えることや、事務処理、雑務などは、お客様が寝た後でやるものだと考えている。
5.他人の何倍も働いて、何倍もの所得をとろう、資産を増やそう、
一生懸命働けば、儲けも大きくできると考えている。
クリーニング店の場合、
1店舗ごとが、10名以下の「生業店」です。
全店舗トータルで「うちは、スタッフ50名の会社だ・・・」と
思い始めた時点で、会社、店の弱体化がスタートします。
会社が大きくなり、ある程度の生活ができるようになってくると、
このような感性が、どんどん薄れてゆきます。
本質的なものをもう一度、自分を含め、そこに働いている人々にしっかりと植えつけることが、
今日ほど必要とされているときはないのではないでしょうか?
私の思うところ、
ご支援先の2世世代(20代から30代)には、このような感覚が薄らいできているようです。
後継者の皆さんには、この「繁盛店エキス」を実践し、
強い会社を作って欲しいと思います。
スマートじゃないけど。。。
2013年11月13日 22:43
繁盛店の特長をまとめたノートをご紹介します。
「繁盛店」とひとことで言っても、
その規模や立地、業種、経営形態によって様々に分類され、
ひとつの繁盛店の特徴をとって、それを他店にあてはめることは、できません。
クリーニング業界に限らず、多種多様な業種の会社を、長年現場で見てきて、
比較的、共通しているもの、
深く突き詰めれば本質では全く同じものを、“繁盛店のエキス”として、抽出してみました。
1.お客様に見えないところは、一に節約、二に節約している。
逆に、目に見えるところには、コストを惜しまない。
2.設備、什器、施設は、とことんまで使い切る。
「使えなくなってから新しくすれば良い」「儲けてから大きくすれば良い」という志向である。
3.他人の金は借りない。無借金経営である。自己資本比率が高い。
4・利益を上げる最大のものは、物でなく、人である。
どちらかと言えば、人使いが荒く、何でもやらせる、遊ばせない。
5.「儲け」は、ガバっと、とるのでなく、小さくコツコツ積み上げるものと知っている。
6・1回当たりの仕入れ量は、少ない。1品目当たりの仕入れ量も、少ない。
7.仕入れの支払いは、現金が結局得をすると知っている。
8.ある単品に圧倒的に強い。単品で地域内のシェアをとりきる。
9.設定した客層が明確である。誰のための店なのか、すぐにわかる。
10.技術力に優れたものがある。他人が真似できないくらい、優れている。
11.買ったときだけでなく、買った後まで何かとサービスしてくれる、気にかけてくれる。
12.見た目の奇抜さがある。店の外装・内装・商品作り・売り方・サービス等の面で、人をびっくりさせることが多い。
13.経営者の人間としての考え方、理想・理念・哲学が、商品・売場・スタッフに反映されている。
14.えらい人ほど良く働いている、下の人はそれを目の前で見て、同じように働く。
15.仕事の成果とその報酬が、かなり一致している。
さて、何個くらい、何割くらい、できていますか?