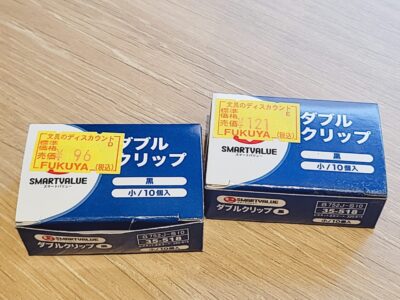2023年4月29日 21:19
「三脚」というものがあります。
主にカメラなどを支えるための、三本足の台である。
脚が1本では支えることができない。どの方向にでも倒れる。
脚が2本でも土台にならない。前後に倒れる。
脚が3本で、初めて支え、土台となることができる。
誰でもわかる物理の原則です。
実は、経営も同じ。
1店舗、2店舗のときよりも、「3店舗」体制となったときから、
全体の売上が、断然、安定するようになる。
先代から多数の店舗を受け継いだ2代目、3代目には、実感することのできない
(だから、学び、想像し、追体験しなければならない)
普遍的な「数の力の原則」である。
私は「三脚理論」と名付けている。
商品。3つのナンバーワン・トップ・アイテム。
店舗。3店舗。
人材。3巨頭。
販路。3つの確立されたルート。
当然、まず、1つの主力が大事である。
次に「3つの強力な柱」を、
とにかく近未来の目標にする。安定度を増すために。
ちなみに、
3つのままが、最も儲かる。利益率が良い。
5、6、、、と増やして行く段階で、徐々に収益性が悪くなる。収益額としては上がる。
4、5、6は、「3」の子分を増やすイメージである。
が、この子分たちの中から、
3分の1くらいの確率で、凄い売上・利益のヤツが出てきて、
また、3の物語が紡がれてゆきます。
10店舗、20店舗、50店舗、100店舗。。となる過程でも、
「3」の理論を、忘れてはならない。
一律・均等に、
多数がぶら下がっている会社=3の理論を実践していない会社は、
どうなるか?
市場が厳しくなると、持ちこたえられなくなる。

ありがたいことに(涙)GWもお仕事。アヒル君とともに向かいます。
※3匹体制にはしてません。
2023年2月26日 21:38
クライアント先の出店候補地にて。
設計プランも佳境に入り、現地にて打ち合わせ。

ロープで実際の配置イメージを正確につかむための手法
=「地縄張り」と言います。
失敗は許されないコンサルタントの仕事です。
近い将来、こうゆうのも、メガネかなんかをかけると、
映画みたいに、びよーーん!と立体映像で、出てくるようになるんでしょうね。
結構、簡単にできるんじゃない?
してもらいたいなあ。
さらに、このメガネを発展させれば、、
過去の作品を記憶させ、
この条件下で、
・最高のコスパを誇るコンサルタント中西なら、こうゆう店を作る。
・芸術家のAさんなら、こんな店。
・建築家のBさんなら、こんな店。
・イケてる経営者のCさんなら、こんな店。
・ダメ経営者のDさんは、こんな店。。
。。みたいなのが、現地を見れば、瞬時に出てくるメガネ。とか、あったら、良いですよねー。
極寒の中、あと数か月後に完成する新店の姿と売上を妄想しながら、
さらなる妄想・空想していました。
2023年1月22日 22:02
1年前の購入時、96円。
今、121円。
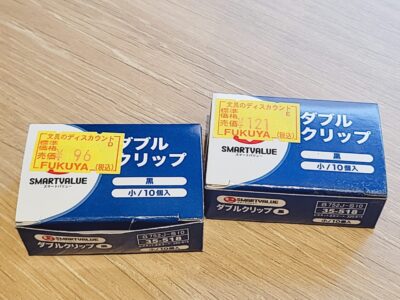
実に、126%の単価上昇。
この文具店の店内の客数は、どうか?
落ちているようには見えない。
売場はそのまま、接客もそのまま。
当然、商品もそのまま。
消費者は、一度は、値上げを許してくれる。
正確に言えば、知らずに、やむやく、買ってゆく。ちょっとした「違和感」を感じながら。
そして、
こうやって、ネチネチと確かめる(ケチ臭い)客がいる。
さて、次回のリピートがあるかどうか?
ケチ臭い客=私は、もう行かない。
かといって、別の文房具屋に行くわけでもない。
異業種=100円均一ショップに、行ってみる。
こうして、文具店の市場自体が落ちてゆく。
「値上げ」は、慎重かつ大胆なる作戦に基づいて決行を。
私がこの文具店のコンサルタントならば、もっと異なる方法の値上げ作戦を立てる。
2023年1月1日 8:54
20代後半のころの話。
資材商さんが集まる総会に、ゲスト講師としてお招きいただいたときのこと。
ある年配の資材商社長が、最近の業界の小売店の経営者に、
こんな「嘆き」を漏らしていた。
「最近の若いモンは“意気に感じる”ということがなくなった」と。
「ワシらが若いときは、誰かの世話になったから、
恩返ししたいから、信用に応えたいから、という気持ちで、損得二の次で、仕事していた」
「資材商が、小売店に対して、支払いを待ってあげたら、その気持ちに応えようと、必死で頑張る小売店ばかりだった」
「ところが、今は、“前回、支払いを待ってくれたから、次も待ってくれるんでしょ。それが当然”という小売店経営者が増えた」
「それどころか、こっちに支払いを残したまま、他の問屋に切り替えるという輩も増えた」
・・・・
以降、そんな「取引切り替え」を受ける列席の同業資材商への
チクチク攻撃(資材商側の商いの道徳にも問題がある・・・的な内容)に発展してゆく・笑
(さすが、老獪な経営者。同業者の集まる総会の場で、それが言いたかったのか!)
が、大事なのは前半「意気に感じる」である。
人生意気に感ず
相手の心意気=積極的に何かをしようとする気持ちに応えるべく、
自分が行動すること。
私は、いつも(勝手に)
意気に感じて、仕事している。
会社の内情を全部、包み隠さず、話してくれたことに対して。
人生の悩みを打ち明けてくれたことに対して。
コンサル料金を払うことを、決断してくれたことに対して。
コンサルの提案をそのまま受け入れ、実行してくれたことに対して。
若いころは、
自分を採用・メンバーに入れてくれたことに対して。
自分を信じて、仕事というステージをもらえることに対して。
まだ会社に利益をもたらす稼ぎができていないのに、給料をもらえていることに対して。
基本、その思いだけでやってきている。と言っても、過言ではないし、
私にそうゆう部分があることを、感じてもらえる経営者さんが、
クライアントになってくれているのだと思います

海へ、朝日を見に行くと、なんと、先客がいました。
たぶん、地元の爺さん。
夜明け前から体操をしていました。
爺さんに「おはようございます!」と、
不意に声をかけられて、恥ずかしい気持ちになる。
なぜ、先に挨拶できなかったんだろうか?
挨拶することを考えていなかった自分に「ダメだな・・」という嫌悪感。
それにしても、
神々しい姿よ・・・・

朝日が昇る前に、去っていった。
また「人生意気に感じる」仕事をいただいたこともあり、
この爺さんと会って、あの資材商の老経営者の言葉を思い出しました。
本年も、よろしくお願いいたします。
2022年12月18日 21:11
ここでシンプルな疑問が湧く。
なぜ、私が「トップ認定」するモンブランの店は、
潰れてゆくのか?
「美味しい」という
自分の感性が間違っているのか?
世間は、マズイ・・・と思っているのか??
トップ認定する「理想のモンブラン」には、条件がある。
・上部に、糸みたいな栗クリーム。
・内部に、生クリーム。
・土台は、メレンゲ。
この3要素だけで、仕上げられており、
3つの味のバランス、食感が一体となっているものである。
一般的なモンブランは、ここにスポンジを入れる。
が、そうなると、普通のモンブランから抜け出せない。
私は、ケーキにおける「スポンジ部分」に対する信頼度が、異常に低い。
未だ、美味しい「スポンジ」、絶妙の「スポンジ」に出会ったことがない。
逆に、もし「スポンジを食べるケーキ」などというアバンギャルドで挑戦的な商品があれば、
間違いなく、飛びついて買ってみる!笑
特に、モンブランにおけるスポンジは、
モンブランを、がっかりさせる原因になりがちなのである。
ところで、
市場から撤退した「トップ・モンブラン」2社には、
上記3要素のみで作られていること以外にも、共通点があった。
1)秋・冬しか、やらない。
2)お客様が取りに来る時間にあわせて、作る。=予約必須
3)だから、店舗に行っても、ない。=存在を知らない人は、知らないまま。
本当に美味しいものを作ろうとすると、きっと、こうなる。
もうひとつ、素人ながら想像するに、
栗クリームと、生クリームだけ。つまりスポンジの力を借りずに、
ケーキを構造体として、維持することが難しいのだと思います。
時間が経つと、重みでペタンとなってしまう。
だから、作り置きできない。
市場に広がらない。
・・・・・・
ああ、俺にコンサル依頼すれば、
このモンブランで、勝つ方法、儲かる方法、
アドバイス&実践フォローしてあげたのになあー。
・・・・・・
コンサル料金は、「モンブラン回数券」でいいよー。
どんな業界にも、
お客様が望んでいる、絶対に喜ばれる。
でも、
手を出すと、倒産する。という「魔性の商品」があります。
気をつけて!
ご支援先とカフェでの打ち合わせ中、
ショーケースに、
「メレンゲ・モンブラン」と「モンブラン・ショート」を発見!
これは、両方食べたいぞー!となり、シェアすることに。

前後で分けず、
左右で分ける。
見た目よりも、本質重視・真実を知りたい専門家は、
どうしても、この分け方となる。

3枚おろしやん・・・・。