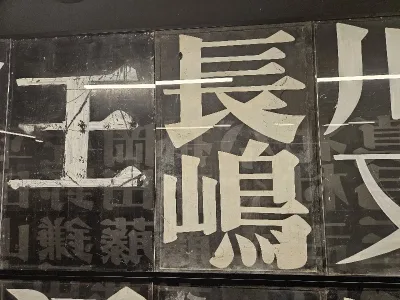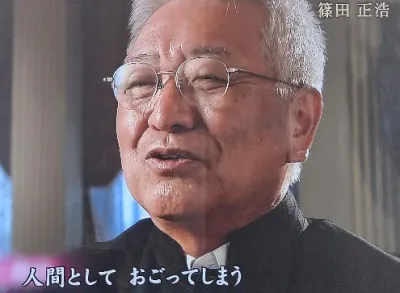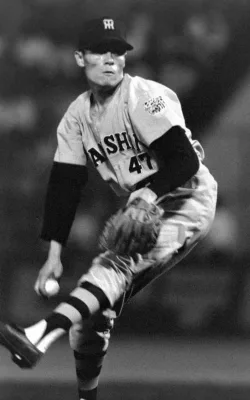2025年12月28日 19:52
一昨年、音楽界の巨匠。
フォークの谷村新司。クラシックの坂本龍一。
お亡くなりになり、私の「レクイエム・シリーズ」に書き留めておきました。
今年は、スポーツ界の各分野の巨星が3名、お亡くなりになりました。
・ゴルフのジャンボ尾崎
・野球の長嶋茂雄
・サッカーの釜本邦茂
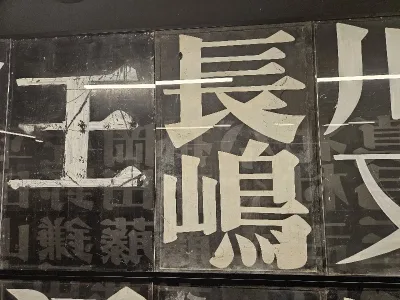
成績や記録はもちろん、記憶に残る天才肌の人物でした。
このレクイエムコーナーは、
故人に対しての賞賛だけを行うものではない。
教訓、学びを得て、前に進むものである。
私は「軍団」を名乗る人、形成する人、それに属する人、群がる人、
チヤホヤする人に、どうも違和感がある。
ジャンボ軍団、たけし軍団、和田アキ子飲み会、
島田紳助ヘキサゴン・ファミリー、
小沢ガールズに、小泉チルドレン、安部派・・・
なぜ、私が、違和感を感じるのか。改めて考えをまとめておきたい。
(嫌い、というほどのことではない。が、自分は作りたくも、入りたくもない。
もし自分の子供が、そうゆうものを、作ろうとか、入ろうとかしたら、絶対やめとけ、距離を置け。とアドバイスする、そうゆう存在である)
「軍団」トップに立つ人は、前に名前がついた時点で、
それ以上の成長をしようとしない傾向にある点。
徒党を組んで、お山の大将となった人物が、さらなる高みを目指し、
他者に乞い、教えを受け、成長する。という可能性は、限りなく少ない。
結果として、所属メンバーの自立が頭打ちとなる。という点にあります。
ジャンボ尾崎は、全盛時、日本で負けなし。
でも、世界に出ると、まったく話になりませんでした。
田舎者的「軍団」志向でなければ、もっと外に目が向かい切磋琢磨すれば・・・
世界でも勝てていたのではないか?と、感じるのです。
軍団内では、社会と隔離された中で評価がなされる。
本人の自主的な思考回路が停止しやすい。
個人の好き嫌いによる評価が起こる。長期的に依存関係で自立しない。
集団意識による問題も起こりやすい
(実際、こうして並べると、起こしていることが多い)
トップに気に入られるかどうか、忠誠心が基準の多くを占める。
常識や反対意見は、裏切りとみなされる。
独自ルール、責任所在が不明確。という点が、その温床である。
能力主義・開放性・個人の自由と自立を重んじる感覚との衝突が「違和感」の正体である。
ジャンボ尾崎=尾崎将司は、元野球選手。
四国・徳島の辺境の地から、海南高校で勝ち上がり、甲子園でも優勝を果たす。
(※公立高校の初出場・甲子園優勝=通算勝率10割は、
原辰徳の父・原貢監督が作り上げた三池工業と、
尾崎の海南高校だけである。選手としていかに逸材であったかの証明である)
高卒で西鉄ライオンズに入団し、将来を嘱望されるも、
同期に超高校級の池永正明がいて、プロの面々と対峙し、限界を感じ、
4年目でゴルフ界へ転向して、大成功を収める。
安心して「一番でいられる場所」を作りたかったのかもしれない。
「軍団」を作りたい人間は、一見、豪快に見える。
が、本質的には、精神がタフでなく、寂しがり屋な面がある。
2025年12月27日 19:10
今年、同じく鬼籍に入った映画監督・篠田正浩さん。
吉田義男さんと、同じようなことを言っておられました。
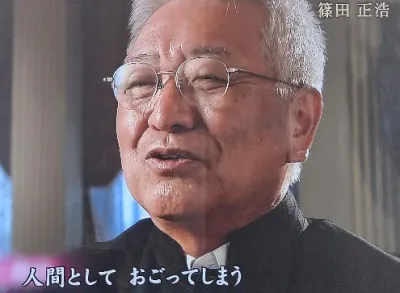
↓↓
勝者はいつもにこやかで自慢話ができる。
敗者はいつも苦い水を飲まされる。
この苦い水を飲んでいる人のほうが、歴史の本質、真実をじかに体験している。
勝者は、有頂天になって見逃してしまっている。
人間としておごってしまう。そのときには自分も見失ってしまう。
負けて絶望することは、たやすい。
イマジンして希望を持つことは、それより困難だけれども、
人間はそれに向かって生きてゆく。後退は許されない。
歴史に逆回することはできない。
前に向かって新しい歴史を刻むしかない。
↑↑
正直、
私とクライアントは、勝つ=勝者であることが、ほとんどである。
敗者になることが、ない。
だからこそ、このことを、ちゃんと肝に銘じておきたい。
本質、真実を見つめ、有頂天にならず、おごらずに。
希望を見出し、後退せず、新しい歴史を刻む。
・チャレンジ=目標を大きく持ち、「そこに達しなかったこと」を
「負け」と感じとるようにしたい。
・小さな失敗、ミス、後悔を「負け」と感じ取りたい。
・法人を構成している人の「負け」を、しっかり感じとりたい。
そのように「負け」を感じて、
いつも油断なく、謙虚な姿勢で臨むようにしたい。
2025年12月21日 19:08
吉田義男さんも、現役時代を知らない阪神の名選手。
「牛若丸」と呼ばれた華麗な守備で、阪神のショートとして。
監督としても1985年「バース・掛布・岡田」の阪神を優勝に導いた。

が、その後、阪神タイガース「暗黒時代」への扉を開けてしまう。
1985年優勝の翌年3位、翌々年1987年には最下位に。
そこから15年間、
ずーっとBクラス(6球団のうち4位以下)、1度だけ2位がある。
その間にも、監督として再登板するも、2年間で5位と6位。
吉田さんは、天国と地獄を味わった。
生前のインタビューより
↓↓
私の野球人生を振り返りますと、1985年に優勝できたことは、
ものすごく大きな思い出です。
同時に、翌々年に最下位になっているんですよ、勝率3割3分1厘という。
この屈辱は、やっぱり誰にも言えないもの、すごく厳しいと言いますか。
でもね、僕は自分で「天国と地獄」と、言ってるんです。
やっぱり、両方味わうことによって、監督業のやりがいというか、
生き甲斐じゃないですかね。
勝つということは、喜んでいただけたということで、
それこそ気持ちの良いものですよ。
しかし負けるということは、勝負の世界ですから当然ですが、
批判され、自分は苦しい。
それは仕方ないですけど、途中で投げたら、僕は負けだと思う。
勝負に負けることが、
人生に負けたことには、つながらないと思う。
↑↑
ジェントルマンで、誰にも優しく、寛容であった吉田さん、
阪神ファンに愛された人物でした。
2025年12月20日 19:46
小山正明さんの全盛期、
阪神タイガースには、「村山実」というエースもいました。2枚看板でした。
サドベック投法と言われるダイナミックなフォームで、
闘志を剥き出しに、剛球を投げ込んでくる名投手。
途中でパ・リーグに移籍した小山さんよりも、村山さんのほうが有名。知名度は上です。
脱力系のフォームから「針の穴を通す」コントロールで
20勝以上をあげる小山さんとは、対極の存在。まさに「両雄」でした。

村山実、通算222勝147敗(プロ14年)
小山正明、通算320勝232敗(プロ21年)
剛球・闘志の村山200勝、
制球・精密の小山300勝。
どれだけ球が速くても、
プロの打者は、一球の「失投」を見逃さず、打ってきます。
100勝分の差は、きっとそこにもあります。
レベルの高い競争になると、剛球、速球。よりも、
「試合に勝ち続ける」ためには、コントロールの良さ。が、大事なのです。
(もちろん一定以上のスピードや技術は必要。という前提で)
コンサルタントにおける「コントロールの良さ」とは何か?
経営者における「コントロールの良さ」とは?
それは、失投=「致命的なミスを犯さないこと」です。
一発、二発、どーんと当て、業績を上げて(短命に終わる)のではなく
人を荒く、ぶん回して使う(使い捨て)でもなく、
長期的に、連続して。丁寧に、安定的に、
お客様の支持=売上を積み重ねること。
派手な剛球、快速球は、拍手を集め、注目も浴びる。
(かく言う私も以前は「剛球・速球派」の投手が好きで、憧れもしていました)
しかし、勝ち星を積み上げるのは、
いつも「当たり前」を外さない投球である。ということに気づきます。
仕事も経営も同じ。
評価されにくいが、最も価値があるのは、
「致命的なミスを一度も犯さずに、攻めること」
小山さんの「300勝の仕事」に学んだことです。
2025年12月14日 17:45
『こうゆう投手は、コンコンとゆうて聞かせても、
まったく、あかんのですわ。もう、ほんまにねー。。』
「精密機械」「針の穴を通す」と呼ばれたコントロールで、
歴代3位・通算320勝をあげた、元阪神タイガースの小山正明さん(享年90歳)。
プロ入りが1953年。引退が1973年(当時、私は0歳)ですから
もちろん、現役時代を知りません。
「野球解説者」として知りました。
家と仕事場の近く、高砂高校の出身と父親から聞かされもしました。
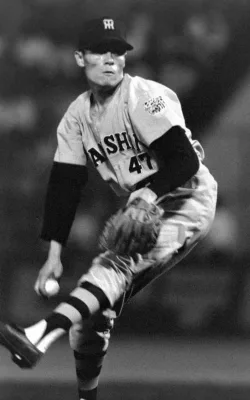
小山さん自身が、
努力を重ね「コントロールの良さ」で一流になった選手だったので、
現役選手で、ストライクが入らない投手、四球で試合を潰す投手が出てくると、
とにかく、厳しかった!!(かつ、面白かった)
たびたび、上記のコメントをしていました。
(ヤクルトの高井雄平投手とかに対して・・・笑)
力任せで投げる投手が、キライ。
制球の良い投手が、スキ。
「自分に似たタイプ」の選手のことを高く評価し、
対極のタイプへの評価は、厳しくなる。
実は、これ。。解説者=評価者、全般に言えることです。
桑田は、身体の小さな選手、打撃・守備も上手な投手が大好きです。
(大きくて筋肉もりもり、力任せ、投げるのみ。には、特に厳しい)
矢野は、気持ちが前面に出て、積極的なプレイをする選手が大好きです。
(淡々として悔しさを見せない、消極的に見える。には、特に厳しい)
宮本慎也は、全体の中で自分の役割に徹し、基礎を大事にする選手が大好きです。
(天賦の才だけ、考えない、流れを切る。基本を疎か。には、特に厳しい)
一定の成功を収めた評価者には、こんな傾向が出てきます。
「類似性バイアス」という「人の性」です。
自分と似たタイプの価値観・経験・行動様式を持つ人を高く評価し、
異なるタイプを低く評価してしまう傾向です。
※先日のブログに当てはめるならば・・・・私の場合、
巡ってきた機会を「つかめるヤツ」「その準備を怠らないヤツ」を評価し
「つかめないヤツ」「その準備が甘いヤツ」に、特に厳しくなる傾向にある。
評価者、リーダーの多くは、
人を評価しているつもりで、実は自分の成功体験を重点基準に採点している。
・自分が誰かを評価するとき
・自分が誰かに評価されるとき
・誰かが誰かを評価しているとき
このことを頭に入れておいて、上手に、精密に「コントロール」しましょう。